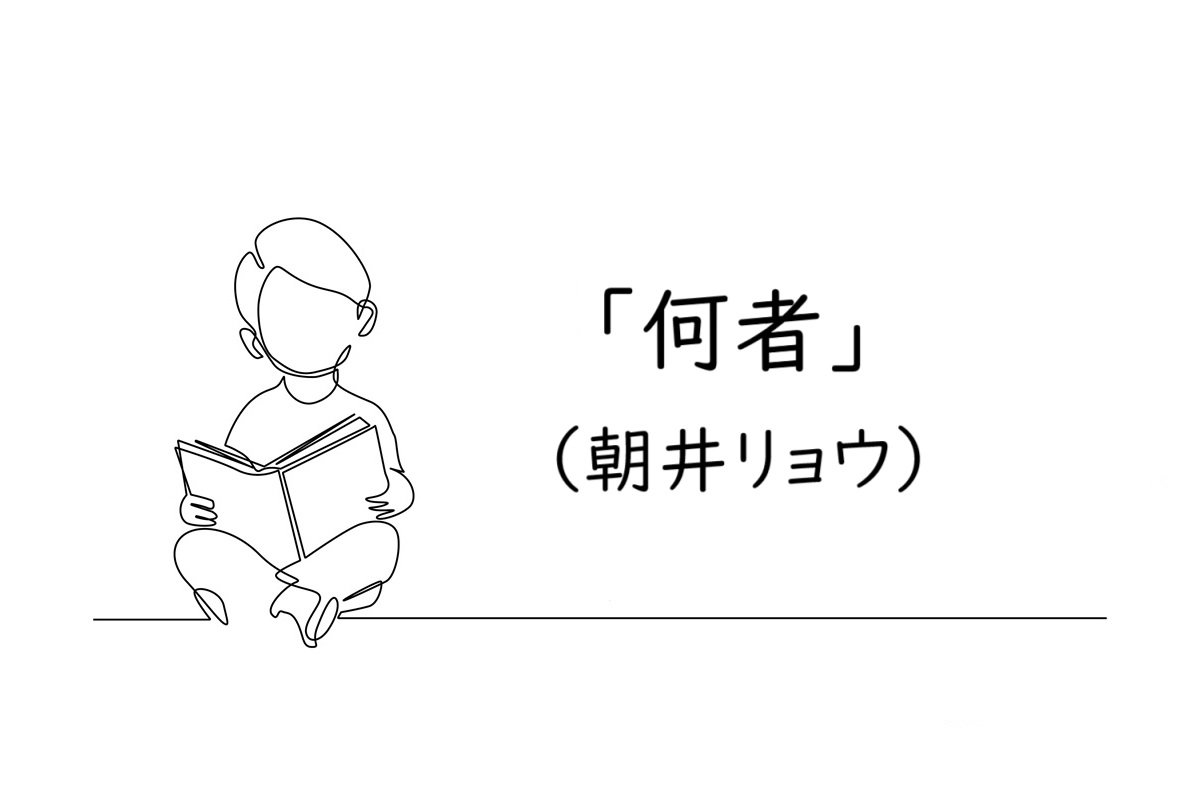
校正者が仕事から離れて読んだ書籍の「読書感想文」
この記事で紹介する読書感想文は、普段は文章をチェックする仕事をしている「校正者」が、仕事から離れて一読者として本を読み、その感想をつづったものです。今回紹介するのは、現役の校正者shimizuさん(40代)が、朝井リョウさんの小説『何者』を読んだ感想です。
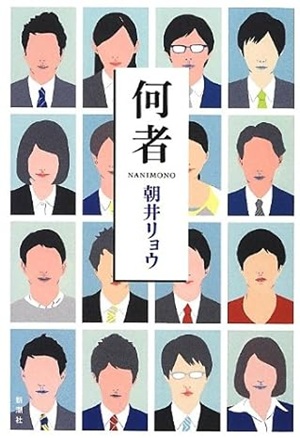
朝井リョウ(2012).『何者』. 新潮社.
校正者が読む『何者』の読書感想文(約1700字)
朝井リョウの『何者』は、現代社会で生きる若者たちが抱える「自己認識」と「他者評価」のギャップを描いた作品です。SNSやインターネットでの自己表現が浸透した現代において、若者たちは「何者であるか」を常に問われるような時代に生きています。この作品は、その現代的なテーマに深く切り込んでおり、自己表現の難しさや他者評価の影響を考えさせられます。
物語は、就職活動に励む大学生たちを主人公に描かれています。彼らの苦悩や葛藤が中心に描かれ、特にSNSを通じた「自己表現」とそれに対する「他者評価」が大きなテーマとなっています。大学生たちは、自己評価と他者評価のバランスに悩みながら生活しており、その姿は非常に現代的で、共感を呼びます。就職活動という一大イベントを控えた彼らにとって、自己評価と他者評価がどれだけ大切か、そしてその両者がどれほど複雑に絡み合うかが描かれています。
登場人物たちはSNS上で自己表現をし、他者の目を気にしながらも、次第に本当の自分を見失っていきます。SNSでの「いいね」や「フォロワー数」が自己評価の指標となり、それがどれだけ虚構であるかに悩む姿は非常にリアルです。彼らは本当に望んでいるものと、SNS上で作り上げた自己像が次第に乖離していきます。この作品は、自己評価を他者の目に委ねることの危険性を鋭く描き出しており、読者に深く考えさせる内容となっています。
また、登場人物たちが自己評価を見失い、不安や孤独を抱える姿も描かれています。SNSでの自己表現が進化する一方で、現実の人間関係や孤独感がより一層際立つようになっていることに焦点を当てています。インターネット上でつながりが作られる一方で、それが本当に深い絆となるかは疑問が残るという現実が浮き彫りになります。登場人物たちはそのギャップに苦しみながらも、どこかで「本当の自分」を取り戻す努力をします。この点に関しては、多くの読者が共感を覚えるでしょう。
本書後半では、登場人物たちが自己表現の意味を再考し、他者との本物のつながりを求める姿が描かれます。SNS上のつながりは一時的なものであり、物理的・精神的な距離感を埋めることはできないことに気づく登場人物たちの成長は、非常に感動的です。本書は、他者との関係性がどれほど大切かを教えてくれます。
この作品では、現代に生きる私たちにとって最も重要なテーマの一つである「孤独」と「不安」が深く掘り下げられています。SNSの普及により、人々は簡単に他者とつながることができる一方で、それが本当に深い心のつながりに繋がるかどうかは分かりません。登場人物たちが孤独感を抱えながらも、リアルなつながりを求め続ける姿に、私たちは現代の人間関係の難しさを痛感します。
この本を読んで私が最も強く感じたのは、「他人と比較して自分を評価することの危険性」です。登場人物たちは他者の目を気にしすぎて本当の自分を見失い、SNSでの「いいね」や「コメント」を求めることが自己評価に繋がっていきます。自己評価を他者の基準に委ねることがどれほど危険であるかを、この本を通じて強く感じました。自分を他人と比べることなく、自分のペースで生きることが本当の意味で大切だということを再認識しました。
本書を通じて伝えられる最大の教訓は、「自己表現」と「他者評価」のバランスの重要性です。現代社会において、SNSを通じた自己表現は当たり前となり、それが私たちの生活に大きな影響を与えています。しかし、自己表現が他者の評価に振り回されてしまうことがないように、自分を大切にすることが最も重要です。自己肯定感を高め、他者との比較に囚われることなく、自分らしく生きることが最終的に幸せに繋がるのだというメッセージが、読者に強く伝わってきます。
この作品を読んで、自分らしい生き方や自己表現の大切さを改めて考えさせられました。登場人物たちが成長し、自己評価を見つめ直していく姿に感動を覚え、私自身も自分を大切にすることの大切さを実感しました。『何者』は、現代に生きる私たち全員にとって、非常に有意義な作品であると感じました。

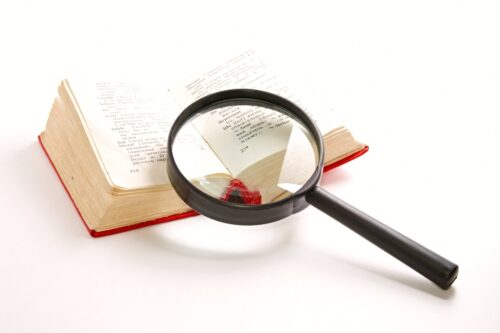

![社会人になって知る日本語の大切さ[超基本:ビジネスシーンで躓かない言葉の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/08/Japanese-words-usage-500x280.jpg)

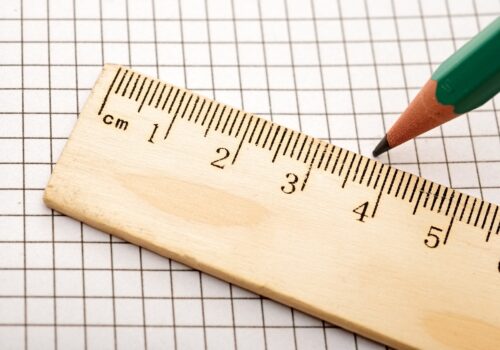

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)

