![校正者の経験値がものをいう場面[あえて赤字を入れない理由と判断基準]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/02/proofreading-experience-required-judgment.jpg)
校正者の経験値がものをいう場面[あえて赤字を入れない理由と判断基準]
校正の仕事では、誤りを見つけた際に赤字を入れて対処します。そして通常、その赤字は反映されるものです。しかし、状況によっては、入れた赤字が反映されない場面があります。たとえ赤字の内容が正しい修正指示であってもです。
なぜこのようなことが起こるのか?その理由には、いくつかの背景や要因が関係しています。
1.「初校」と「最終の校正」の温度差
校正にはいくつかの段階がありますが、その中でも初校と最終工程の校正では、赤字の扱い方が異なる場合があります。
■初校の場合
初校は、文章全体や体裁に関する誤りを見つけて修正する段階です。この段階では、赤字で指摘した内容は基本的にすべて反映されます。初校はそれ以降の土台となるため、この段階での仕上がり具合が最終的な品質に大きく影響してきます。
そのため間違いがないかくまなく確認し、赤字が入ればその通りに修正されることになります。文字だけでなく、体裁面、デザイン的な面でも完成度を高めるため十分な注意が払われます。(※場合によっては初校と再校の2段階でこのような作業を行います)
■最終工程の場合
一方で、最終工程の校正は、仕上げ段階にあたります。この段階では、時間的制約もあり、優先度が低いとされる誤りは見送られるケースがあります。赤字で指摘した内容が必ずしも反映されるとは限りません。
具体的には次のような場面です。
- 全体的な見た目に大きな影響を与えない軽微な誤り
- 誰も気に留めないような細かい不整合
- 修正によるメリットがほとんどないと判断される箇所
最終の段階では、限られた時間の中で重要なポイントに集中する必要があるため、重要度の低い赤字は不採用となることもあります。この赤字を採用するかどうかの判断は、制作や校正の責任者の判断に委ねられる場合が多いです。
以上のように、初校は作品の完成度を高めるための「土台作り」の段階であり、赤字の内容を反映することが求められます。一方、最終校正は「仕上げ」の工程であり、時間や優先度の都合上、一部の赤字が反映されないこともあります。
ただし、初校であっても、提出直前に見つかった誤りは再校時に回して直すということもあり、最終段階の切羽詰まった状況であっても、誤字脱字のような明らかな誤りを見つけた場合は、当然赤字を入れます。またクライアントから修正指示が入った場合も従う必要があります。明確な線引きはできず、臨機応変な対応が求められます。
このような状況を熟知している校正者なら、初校のときには違和感があれば書き込むものであっても、最終の段階ではあえて指摘をしない判断を下す場合があります。
2. 判断力が必要な赤入れ
前述したように、赤入れの必要性や優先度を、現場の状況に応じて判断する場面があります。すべての誤りを指摘するわけではなく、場面によって赤字を入れるか否か対処することがあります
<赤字を入れるか否か状況によって判断がわかれるもの>
・複数の同じ間違い
たとえば、文末の不揃いが一つだけで目立たないのであれば、赤字を入れないこともあります。一方で、文末の不揃いが複数箇所にわたる場合は全体の見た目に影響するため赤入れが必要となります。
・目立つ位置での表記ゆれ
離れたページにある言葉の表記ゆれは、重要度が低いため赤字を入れないこともありますが、見出しやタイトルなど大きな文字や目立つ箇所で表記がゆれている場合は、読者の心象を損なうリスクがあるため赤入れの対象になります。
<赤字が流される傾向にあるケース>
一方で、文章や誌面の仕上がりに大きな影響を与えないと判断されるものについては、赤字が流される傾向にあるため、校正者としても、あえて赤字を入れないという選択をすることがあります。
具体的には次のような誤りです。
- 図版や画像の位置がごくわずかにズレている
- 文字間隔の細かい調整
- 行間のわずかな違い
- トリミング(画像の切り取り)のわずかな誤差
- 余白のサイズがわずかに異なる
- 文意に影響しない読点の抜けや送り仮名の違い
- 文頭や文末での微妙なズレ(半角以下程度の違い)
- 離れたページにおける表記ゆれ(文章全体に大きな影響がない場合)
- 言葉の使い方が正確ではないが、許容範囲内とされるもの(ら抜き言葉など)
この際の赤字を入れるべきかどうかの判断は、一律に決められるものではありません。次のような要因が影響するため、総合的な判断力が必要になってきます。
- 過去の事例
→ 似たような案件でどのような対応が取られたか - 媒体の特性
→ 雑誌や書籍、広告など、媒体ごとの傾向や目的 - 関係者の基準
→ 編集者やデザイナーなど他の関係者の判断基準 - クライアントの意向/校正に求められる品質
→ クライアントが何を重視しているか(正確性・スピード・コストなど)
総合的な判断力を身につけるには経験の積み重ねだけでなく、周囲とのコミュニケーションも大切になってきます。
ここで誤解してはいけないのは、些細な間違いだから「これぐらいだったら大丈夫だろう」という安易な判断ではないということです。
3. 最終工程での「疑問出し」は要注意
最終の工程では、赤字で指摘した箇所であっても流される可能性があるため、「疑問出し」は特に要注意です。
通常時の校正において、「赤字」は重要度が高く、優先して対処されるべきものです。一方、「疑問出し」は、明確な修正指示というよりも確認や再検討を促す性質が強いものです。赤字に比べると重要度は低くなります。
そのせいで、最終段階に差し掛かった場合や時間がない状況では、尚更赤字にばかり意識が行き、疑問出しへの注意が薄れる傾向にあります。
こういった事情から、最終の工程で重大な疑問が出てきた場合は、校正ゲラに書き込むだけでなく直接担当者に説明するなどして、見過ごされないように注意を促すなどの工夫も必要です。
おわりに
この記事で説明した例は、現場の方針や媒体にもよりますが、「特殊なケースと感じる方」と「よくわかるという方」で二極化するかもしれません。
時間と予算に制約がある中で、タイトなスケジュールでは、優先度が高い赤字に対応せざるを得ず、時には致命的ではない赤字が流されることもあります。また予算が限られている場合には、校正作業にかけられる時間が制限され、十分な確認を行えないケースもあります。
理想としては、すべての赤字が正確に反映され、疑問出しも適切にジャッジされることですが、現実にはスケジュールの制約や予算の都合といったさまざまな要因が絡み、必ずしも理想通りに進まないことがあるのが実情です。

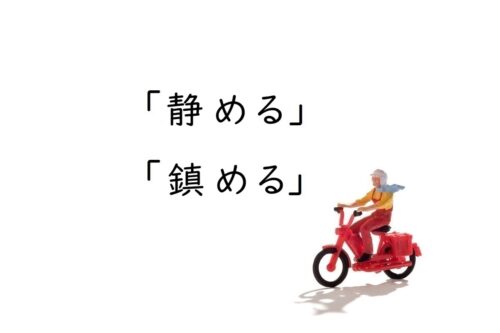






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)
![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

