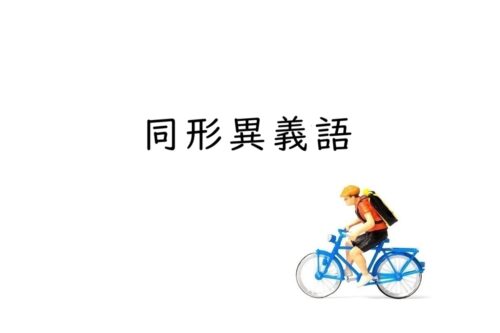![読み合わせの意味・具体的なやり方・注意点[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Reading-together-in-proofreading.jpg)
目 次
読み合わせの意味・具体的なやり方・効果[例文解説]
▼ 読み合わせとは
「読み合わせ」と聞けば、映画やドラマの役者さん達が台本を読み合い稽古するイメージが強いかもしれません。ですが、校正にも読み合わせという校正技術があります。
読み合わせ校正は、校正者だけでなく色々なビジネスの場面で使われるものです。資料や文書に間違いがないか、二人一組になって読み合わせで確認するということはよくあります。
三省堂の大辞林で調べると、一番目に読み合わせ校正のことが説明されています。
■ よみあわせ
① 読み合わせて校合(きょうごう)すること。 「 -校正」
② 演劇の稽古で,俳優が脚本の各自の持ち場を互いに読み合い,台詞(せりふ)のやりとりをすること。
■ きょうごう
写本・印刷物の文字や記載事項を、基準となる本や原稿と照らし合わせてその異同を知ること。また、それによって訂正したり相違を書き記したりすること
【出典:三省堂 大辞林 第三版】
1. 読み合わせ校正の基本的なやり方
読み手(原稿を読む側)と聞き手(校正ゲラを確認する側)の2人がペアになって確認作業をしていきます。読み手が原稿を読み、聞き手は読み手の音読に合わせて文章を確認していきます。
簡単そうに聞こえますが、読み手には高いスキルが要求されます。校正初心者には向いていない作業です。読み合わせ校正をするにあたっては、同音異義語・間違えやすい漢字や送り仮名・表記ルールなどを知っておかないといけません。
それらを知らないで読み合わせ校正をすると、作業効率が悪いばかりか、間違いだらけになる恐れがあります。
2. 読み合わせ校正の具体的なやり方
テキスト原稿をオペレーターが手入力したとします。それを、読み合わせ校正で確認していくやり方を説明したいと思います。
用意するものは、元のテキスト原稿と校正用のゲラです。
原稿を読むのが、Aさん、
校正ゲラを確認するのが、Bさんとします。
■ Aさんが読むテキスト原稿
1.柱枠の組立て
ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。
最下段は下から2つ目と3つ目の角孔にはめ込んでください。
■ Bさんが確認する校正ゲラ
1.柱枠の組立て
ベースプレ-トを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。
最下段は下から2つ目と3つ目の角孔にはめ込んでください。
※赤字の箇所は、オペレーターが「音引き」を「ダーシ」に入力間違いしたところです。
上記の文の下線部文を「読み合わせ校正」で確認していきます。
■ Aさんの音読
「すうじのいち。ぴりおど。はしらわくの。くみたて。くみたてのおくりがなは、てのみ。かいぎょう。かたかなで、べーーすぷれーーと。をとりつけた。しちゅう。すうじのに。ほんを。どくてん」
というようになります。
このAさんの音読に合わせて、Bさんは校正ゲラを確認していきます。
■ Aさんの音読:下線部分の解説
1. 組立て → くみたて。くみたてのおくりがなは、てのみ
送り仮名はバラつきが起こりやすいため送り仮名が何であるかを明確に伝える必要があります。
2. ベースプレート → べーーすぷれーーと
音引きは、拗音と誤解されないよう意図的に長く発音します。
3. 取り付け → とりつけ
本来なら1の「組立て」のように送り仮名の説明が必要ですが、ここでは「とりつけ」と言うだけで送り仮名が何であるかを、あらかじめルール決めしています。
どのようなルール決めかは次のようになります。
- 「取り付け」なら「とりつけ」と読む
- 「取付」なら「とりふ」と読む
- 「取付け」なら「とりふ。おくりがなのけ」と読む
このように、読み合わせ校正はあらかじめルール決めしておかないと時間が掛かり非効率なものになります。
ルールは、各社・各媒体で独自で決めているため、上記の方法以外にもやり方はあります。
3. 読み合わせ校正の注意点とポイント
<注意点>
・読み手の音読するスピードは、普通に話すよりもやや遅いぐらいのスピードです。そのため、読み手と聞き手の阿吽の呼吸が必要になってきます。
・読み手は聞き手に伝わるように、言葉だけで漢字の送り仮名など、文字情報のすべてを説明しなくてはいけません。間違えそうな文字が出てくれば、それを咄嗟に判断して、聞き手に伝わるように説明する必要があります。
・太字や斜体、級数など、文字の体裁までは伝えません。
ただ、下のように文章内で強調されている文字に関しては、読んで教えてあげたほうが親切です。
「業界No.1の実績」
・あらかじめ細かなルール決めが必要。ルールのない読み合わせ校正は非常に効率が悪くなってきます。
<聞き手側の注意点>
聞き手だからといって、単に文章を目で追って確認だけしていればいいわけではありません。間違えやすい送り仮名などがあれば「この送り仮名は?」と聞く必要も出てきます。読み手が、読み間違えることも十分考えられます。
例文では、「ベースプレート」の音引きが「ダーシ」になっています。これは、原稿だけを見ている読み手のAさんには絶対にわかりません。Bさんが見つけるしかありません。
このように、読み合わせ校正は、読む/聞く(確認)だけでなく、非常に高度な技術を要します。そのため、用語が統一されている媒体や比較的難易度の低いものに限定されてきます。
※上記の例文は、読み合わせ校正には不向きな部類なものになります。
▼ 読み合わせ校正のポイント
1. 読み手には高いスキルが要求される
2. 聞き手だけにしか見つけられない間違いがある
3. 校正する媒体を選ぶ
日本エディタースクール出版部『実例 校正教室』でも読み合わせ校正の難しさが次のように記されています。
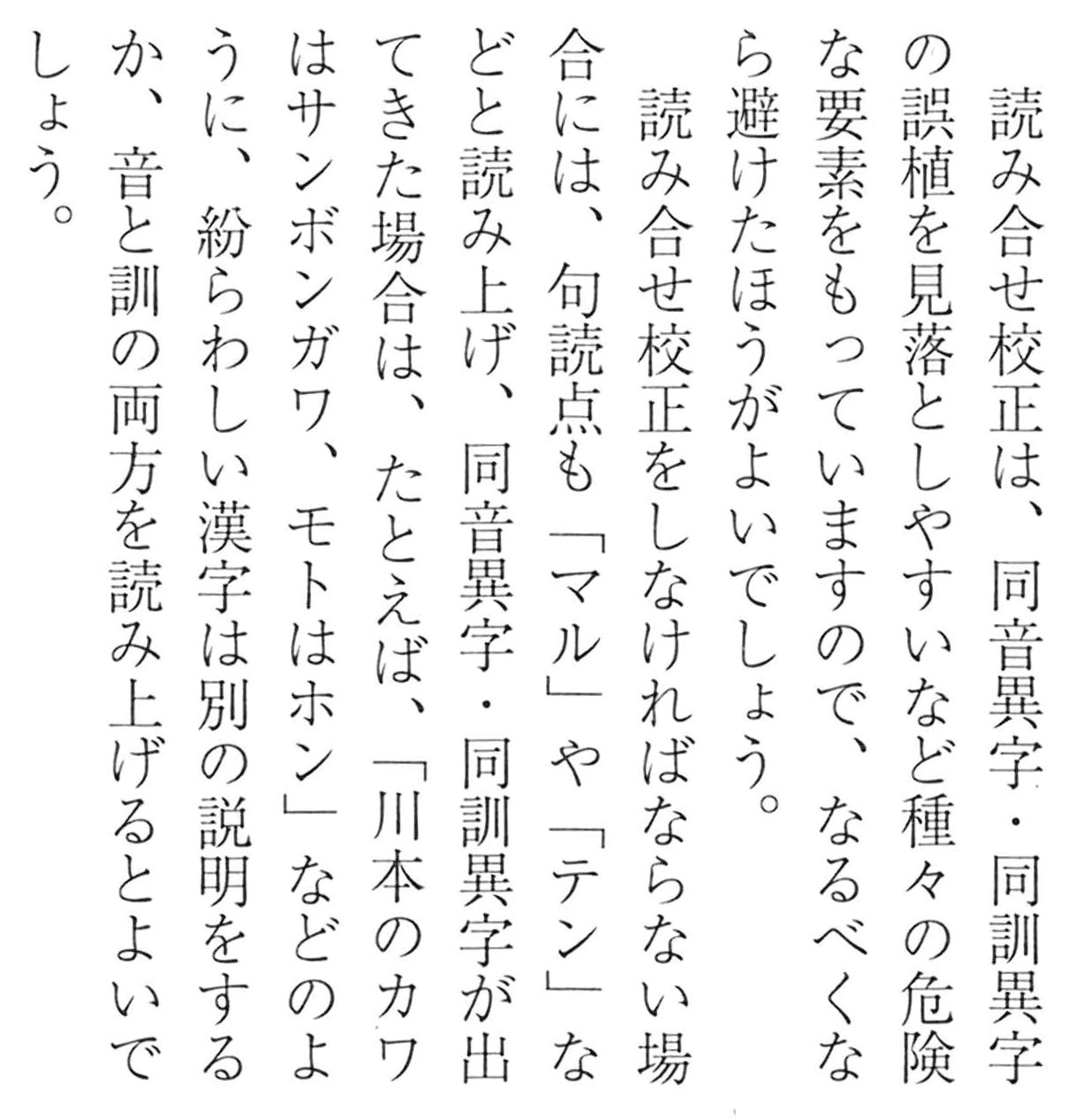
【出典:日本エディタースクール出版部_実例 校正教室 P.20】
4. 読み合わせ校正の巧みなテクニック
前述の「取付」を「とりふ」と読むのは、読み合わせ校正をスムーズに進めるためと、送り仮名の有無を一発で聞き手に伝えるためのテクニックです。その他にも次のようなものがあげられます。
1.「ください」と「下さい」
読み手が「ください」とだけ言うと、聞き手は「下」の字が漢字かひらがなか判断がつきません。
この場合、
ひらがなの「ください」は「ください」とそのまま読み、
漢字の「下さい」は「したさい」と読み分けます。
※「下さい」の場合に「かんじでください」と言ってもいいですが、頻繁に出てくるバラつきやすい用語はルール決めをしておいたほうが効率がよいです。
2. 間違えやすい漢字の場合
〇 加湿器 × 加湿機
この場合の読み方としては、「かしつうつわ」と読むことで「器」と「機」の違いを聞き手に伝えます。これも、間違えやすい漢字を相手にどう伝えればよいかという読み手の技量が試されます。
〇 乾電池 × 乾電地
「かんでんいけ」と読みます。
このような間違いはレアなケースですが、混同しやすい漢字などは意図的に読み方を変えて工夫します。そのため、起こりやすい間違いや使用頻度の高い用語などの蓄積が必要になってきます。
3. 数字
「0000071」
読み方としては、「ぜろ、ぜろ、ぜろ、ぜろ、ぜろ、しち、いち」ではなく、
「すうじのぜろがごこ、なな、いち」と読んだほうが聞き手に伝わりやすいです。
ここでの読み手のポイントは次のようになります。
・数字の「0」とアルファベットの「O(おー)」との違いを伝えること
・連続する数字を読み手が見間違わないように個数を伝えること
・「7(しち)」と「1(いち)」だと聞き間違えやすいので「7(なな)」と「1(いち)」と伝えてあげること
4. アルファベット
「B」を「ビー」、「D」を「ディー」と読むと聞き間違えが起こりやすいです。
「D(ディー)」と「T(ティー)」も同様です。
そのため、次のような読み分けが必要になってきます。
「B」 → 「ビー」
「D」 → 「デー」
「T」 → 「テー」
海外映画などで、アルファベットを相手に正確に伝えるために単語の頭文字を取って伝える場面はよく見られます。
「A」を、アルファの「えー」
「B」を、ブラボーの「びー」
「C」を、チャーリーの「しー」
「D」を、デルタの「でぃー」
「E」を、エコーの「いー」
【参考サイト:Wikipedia_通話表】
> Phonetic code[PDF]
5. 記号類
「 」、『 』、( )、〈 〉、【 】のような文章中に頻繁に出てくる記号も明確にいえる必要があります。
・「 」 かっこ かっことじ
・『 』 にじゅう(かぎ)かっこ かっことじ
・〈 〉 やまかっこ かっことじ
・【 】 すみつきかっこ かっことじ
・( ) ぱーれん かっことじ
※読み合わせの場合、とじのかっこは正式名称を言わなくても「かっことじ」に簡略化します。
5. 読み合わせ校正は効果がある?効果がない?
読み合わせ校正には校正者が2人必要になります。また、読み手には高い校正スキルが必要になってきます。さらに、読み手/聞き手同士で、決められたルールを共通認識として持っておく必要があります。
時間や精度の面では、正確な計測ではありませんが、一人での校正に掛かる時間を100とすれば、読み合わせでの校正は、40~60ぐらいの時間ですむ感じです。
ただ、これも条件により左右されます。校正者のスキルにより時間のバラつきも大きくなります。精度の面でも、校正者の経験値次第ということになってきます。
そのため、一人で校正するのと二人で読み合わせ校正するのとでは、どちらが効率的かは明確にいえないところです。
読み合わせ校正のまとめ
読み合わせ校正のデメリットとして、次のようなことが考えられます。
・校正者が必ず2人いる
・事前のルール決めが必要
・精度が不明
読み合わせ校正に慣れた人を確保できて人手を掛けられるというのであれば、メリットも大いにあります。
ですが、現状を考えれば、人手やルール決め・媒体を選ぶ・経験値が必要ということからして「読み合わせ」の校正技術は廃れ行くものとなっていくでしょう。
※ここでの例は、校正者がする読み合わせ校正を述べたものです。他の職種の方がする読み合わせ校正は、この限りではありません。

![Wordの音声読み上げ機能で文章のミスを防ぐ[動画で解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Text-to-speech-reading-with-Word.jpg)

![三点リーダー・二点リーダーの意味と使い方[校正記号の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/three-point-leader-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

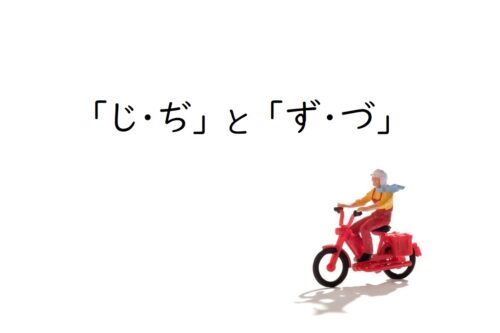
![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)
![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)
![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)