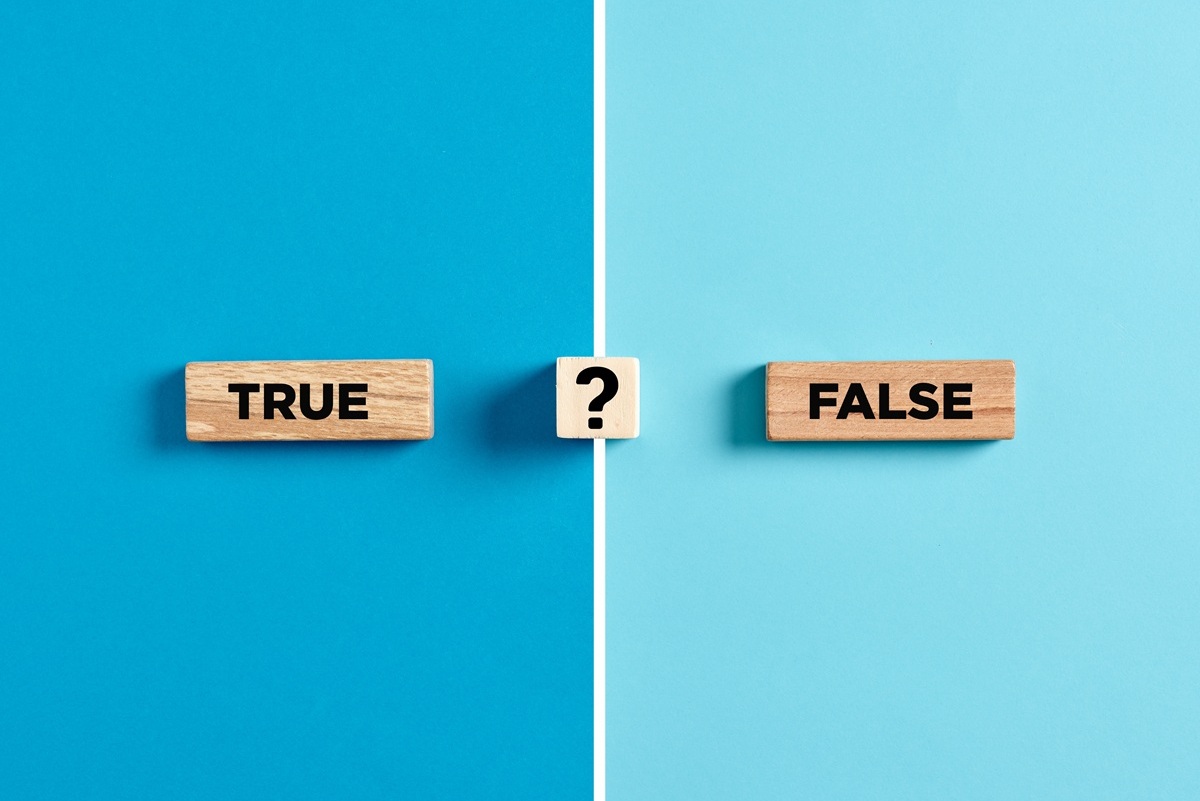
目 次
【ファクトチェックの重要性】本当か?嘘か?知っておきたいフェイクニュースの見極めポイント
近年、インターネットやSNSの普及によって、膨大な情報に瞬時にアクセスできるようになりました。しかしその一方で、誤情報や意図的なデマもまた、同じスピードで拡散されやすくなっています。こうした虚偽の情報は人の判断や行動に大きな影響を及ぼしかねないため、正確な情報を見極める力がますます必要になっています。
そこで重要となるのが「ファクトチェック」です。ファクトチェックを日常的に行うことで、インターネットやSNSで広がる偏った意見や誤ったデータに惑わされにくくなり、より信頼できる情報に基づいた判断ができるようになります。
「多くの人が言っているから正しい」
「信頼している人が言っているから間違いない」
「専門用語が使われているから正しそう」
情報の拡散の速さや量は真偽とは無関係で、たとえ信頼されている人でも、本人が悪意なく誤情報を拡散してしまうことがあります。専門的な言葉や数値が並んでいても、それが正確な根拠に基づいているとは限りません。印象操作の可能性もあります。
フェイクニュースが信じられるわけ!?
そもそも、どうして人はフェイクニュースを信じてしまうのか。これは、人の感情や思い込みが判断を曇らせるせいだと考えられます。フェイクニュースに騙される背景には、次のような心理があります。
① 確証バイアス
・自分の信じたい情報だけを信じてしまう傾向
② 感情的トリガー
・怒りや恐怖、不安を煽る情報は記憶に残りやすく、信じやすい
③ 繰り返し効果
・何度も見た情報は本当のように感じてしまう
④ 情報過多による判断疲れ
・「全部チェックするのは無理だ」と思ってしまう
またフェイクニュースやデマの拡散には、感情や人間関係、SNSの仕組みが大きくかかわってきます。デマの連鎖的拡散には以下のパターンが顕著にみられます。
① 感情を刺激する(怒り・不安・共感)
・「危険」「裏がある」「かわいそう」などの言葉で心を揺さぶる
・冷静な事実よりも、感情的な言葉のほうが拡散されやすい
② 見慣れた人物からの発信(信頼効果)
・有名人、友達がシェアすると「自分も信じていい」と感じる
・「○○から聞いた話だけど……」という言い回しが信憑性を生む
③ SNSの構造
・「いいね」「リツイート」が感情的・派手な投稿に集中しがち
・SNSのアルゴリズムが刺激の強い情報を優先的に表示するため拡散が加速
他にも、フェイクニュースに騙されやすい人の特徴として次のような点があげられます。
① SNSが主要な情報源になっている
・フィードで流れてくる情報を、ニュースのように捉えてしまう。
② 公式情報と個人の投稿の区別がつかない
・フォロワーの多い人や、見た目がプロっぽい投稿に影響されてしまう。
③「正しさ」より「面白さ」や「共感」を重視する
・情報の正確性よりも拡散性やバズを優先してしまう。
④「検索結果の上位=信頼できる」と思い込む
・検索結果の順位が必ずしも信頼性の高さを示すわけではありません。
ファクトチェックをする際の注意点
ファクトチェックは、誰かが言ったことや広まっている情報が、本当に事実に基づいているのかを確かめる作業です。ニュースやSNSなどで見かける発言や主張に対して、「それは本当なのか?」という視点で、信頼できる資料やデータを使って客観的に調べます。
ここで注意が必要なのは、ファクトチェックは「事実」に関する確認に限られるということです。たとえば、「この制度は良いと思う」「この政策は間違っている」といった個人の意見や評価は、正しいかどうかをファクトチェックで判断することはできません。なぜなら、意見や感想は人によって異なり、事実のように客観的な検証ができないためです。ファクトチェックは「事実に関する確認作業」であって、個人の意見や価値判断、感想などの主観的な表現について、その正しさや妥当性を評価するものではないということです。
つまり、発信された内容に対して異なる考えを持っていても、それが単なる「意見」であれば、ファクトチェックの対象にはなりません。「事実」と「意見」をしっかり区別することが、正確な情報を見極めるうえで非常に大切になってきます。
ファクトチェックの5つのステップ
正しい情報を見分ける力は、日常のニュースやSNSで流れてくる情報の真偽を判断するうえで役立ちます。以下、ファクトチェックの基本的な手順をご紹介します。
1. その情報は「事実」?それとも「意見」?
ファクトチェックを始める第一歩は、「情報の性質を見極めること」です。まずは、事実か意見かを区別することから始めます。「これは事実なのか?」「それとも意見や主張なのか?」を分けるようにしましょう。
•「事実」と「意見」の見極め
事実とは?
・数字やデータ、公式な発表など誰が見ても同じ内容になる情報
・第三者が調べて「本当だ」と確認できる
意見とは?
・「〜だと思う」「〜に感じる」など、その人の気持ちや考え方
・他の人は違う考えを持っていることがある
<例1>
「昨日の最高気温は29度だった」→ 事実(天気の記録という客観的なデータ)
「昨日はとても暑かった」→ 意見(暑さ寒さの感じ方は個人によって異なる)
<例2>
「2024年12月1日現在の東京都の人口は約1,420万人だった」→ 事実(統計で確認できる客観的なデータ)
「東京は人が多すぎて住みにくい」→ 意見(他の都道府県より人口が多いのは事実だが、住みやすさは主観的な評価)
このように、事実とは、検証できるデータや記録に基づいたものを指します。観測結果や統計、公的な発表などで裏付けられる情報です。一方で、意見にはその人の価値観や感情が含まれていることが多く、必ずしも客観的ではありません。
ここで注意したいのは、一見すると事実のように見える意見もあるということです。たとえば「この政策は失敗だ」という表現は、特定の事実を根拠にしているように見えるかもしれませんが、「失敗」とするかどうかは評価や立場によって異なるため、意見にあたります。
情報の内容が検証可能な「事実」なのか、主観的な「意見」なのかを見極める習慣を普段から持っておくとフェイクニュースにも騙されにくくなります。
2. 信頼できる情報源を選ぶ
正しい情報を手に入れるには、信頼できる情報源を見つけることが欠かせません。「その情報は、どこから来たのか?」を見極めることです。
一般的に以下のような情報源は、信頼性が高いといえます。
・公的機関や大学・研究機関が発信している
・元のデータや根拠(出典)がはっきりしている
・事実と意見が明確にわけられている
・過去の報道や内容に一貫性がある
※信頼できるサイトは、以降の「ファクトチェックに役立つサイト」の項目をご覧ください。
さらに、情報に対して次のような視点を持っておくと真偽の見極めのポイントとなります。
・情報が最新か?(定期的に更新されているか)
・第三者や機関から高く評価されているか?(引用数など)
・発信のタイミングや背景が自然か?(特定の意図がないか)
情報源を一つに絞らないことも大切です。一つの情報だけで判断せず、複数の信頼できる情報源を比較することで、偏った見方や誤解を防げます。
3. 元の情報にたどり着く
インターネットの情報には、誰かの「意見」や「要約」が多くあり、「自分の解釈」を通して情報を伝えていることがよくあります。正しい情報を見分けるためには、「その情報のもとになった一次情報(=オリジナルの出典)にたどり着く」ことが欠かせません。
一次情報とは、最初に発表された元の情報やデータのことです。たとえば、ニュースで「専門家が□□と言っていた」と書かれていたら、その元の専門家の発言や会見動画、論文などが一次情報となります。
動画やインタビューの一部だけを切り取って偏った情報が拡散されるケースも多くあります。発言者の意図を正確に知るためには、「全文を読む」「前後の流れを見る」などして文脈を把握することが大切です。
一次情報に直接触れることで、
・発言やデータの本当の意味がわかる
・文脈(どんな状況で言ったか)を理解できる
・誤解や歪曲された情報を見抜く力がつく
などファクトチェックに必要な力が身につきます。
• 情報を効率よく探す検索テクニック
Webサイトで一次情報を探すときに役立つ検索方法を紹介します。(※Google Chromeでの検索)
① 信頼できるドメインに絞って検索する
検索方法 >【 site:go.jp フェイクニュース 罰則 】
→ 日本政府の公式サイト(.go.jp)内だけを検索
他にも「site:ac.jp(大学)」「site:who.int(WHO)」などで絞ることもできます。
② 知りたい正確なフレーズを「" "」で囲んで完全一致で検索
検索方法 >【 "ダブルチェックの有効性" 】
→「" "」で囲んだ文を含むページだけをピンポイントで検索できます。
③ タイトル検索で的確に
検索方法 >【 intitle:統計 出生率 】
→ タイトルに「統計 出生率」が含まれるページに限定して検索できます。
④ 学術情報を活用する
→『Google Scholar』を使えば、専門家による論文や学術研究を検索できます。
※さらに検索のコツを知りたい方は次の記事をご覧ください。
4. 複数の情報を見比べる
情報が正しいかどうか確かめるためには、一つの情報だけを信じるのではなく、他の情報と見比べる(=クロスチェック)ことが非常に大切です。
「このニュースは本当に起きた?」「この人の発言は正しいの?」「この数字は本物?」といったように、何が事実か知りたいのかをあらかじめ整理しておくと調べやすくなります。
同じニュースでも、新聞、テレビ、政府の発表、専門家の解説など、いろんな人や団体が違う角度から伝えています。そういった複数の情報源を比べてみることで、情報の偏りや間違いに気づけるようになります。
• クロスチェックのコツ
① 異なる立場の情報を比べる
同じ話題について、政府・専門家・メディアなど立場の違う人たちの意見に触れることで、偏った見方を避ける手助けになります。
② 数字や内容の「一致/不一致」を確認する
いくつかの情報源を見て、書かれている内容が同じか?違うか?をチェックします。違いがあるときは、「なぜ違うのか?」を考えてみることが大事です。
③ 情報源の信頼性を確認する
その情報を出している人物や団体はこれまでに信用できる発信をしてきたかをチェックします。一般的に公的機関・大学・専門メディアなどは、信頼性が高いことが多いです。
④ 情報の新しさや背景も見る
古い情報ではなく、できるだけ新しくて、そのときの状況に合ったものかを確認します。内容が古くて今の状況に合わないものもあります。
5. 誤解されやすい情報の特徴
情報のなかには、一見正しそうに見えても、よく読むと誤解を招くように作られているものがあります。こうした情報にだまされないためには、誤解されやすい情報の特徴を知り、それに気づく目を養うことが大切です。
• 誤解を生む情報の主な特徴
① 数値やグラフだけで判断を誘導する
たとえば「犯罪件数が倍増した」と聞くと不安が煽られますが、実際には「1件→2件」など母数が小さいケースもあります。また、棒グラフや円グラフが恣意的なスケールで描かれていることもあります。
② 引用元が不明確または曖昧
「専門家によると」「研究ではこう示されている」と書かれていても、実際の出典が示されていない場合、その情報の信頼性は低い可能性があります。
③ 感情をあおる言葉や演出
「これは陰謀だ!」「恐ろしい事実が判明!」など、煽情的な言葉を使って不安や怒りを引き出そうとする表現は、冷静な判断を妨げる要因になります。
④ 一部の事実だけを強調する
本来は全体の流れや前提とセットで理解すべき情報なのに、一部分だけを切り取って強調している場合には、誤解を招く可能性があります。
ファクトチェックに役立つサイト
インターネットにはたくさんの情報があり、その情報が正しいかどうかを見分けるのも時間を要します。ここでは、ファクトチェックに役立つ信頼性の高いサイトを紹介します。
① ファクトチェックの専門メディアや団体
- ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)
日本におけるファクトチェックの推進団体。基礎知識やチェック実例、評価基準などが学べます。
→ https://fij.info - ファクトチェックナビ(FactCheck Navi)
日本語で使える総合的な検索ツール。メディアの検証記事をまとめて検索できます。
→ https://navi.fij.info - 日本ファクトチェックセンター(JFC)
国内の報道機関や専門家によるファクトチェックを集約・公開している公式サイトです。
→ https://factcheckcenter.jp - BuzzFeed Japan ファクトチェック
ニュースサイトBuzzFeedの日本版によるファクトチェック記事が掲載されています。
→ https://www.buzzfeed.com/jp/badge/factcheckjp - Google Fact Check Explorer
世界中のファクトチェック記事を横断的に検索できるGoogleのツールです。
→ https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
② ファクトチェックの報告書・資料(※ファクトチェックの勉強に役立つ)
③ 公的機関・政府資料の検索
- 厚生労働省
医療・福祉関連の情報を掲載。
→ https://www.mhlw.go.jp - 消費者庁
詐欺や誤情報に関する注意喚起など、生活に直結する情報を掲載。
→ https://www.caa.go.jp - 総務省 統計局
社会動向に関する公式な統計データを閲覧可能。
→ https://www.stat.go.jp - e-Stat(政府統計ポータル)
国が公表するあらゆる統計情報を一括検索。
→ https://www.e-stat.go.jp - 内閣府公式サイト
政府の政策・発表の一次情報が掲載。
→ https://www.cao.go.jp
④ 調査・文献
- CiNii(NII学術情報ナビゲータ)
学術論文や書籍を検索できるデータベース。信頼性の高い学術情報を検索可能。
→ https://ci.nii.ac.jp - J-GLOBAL(科学技術総合リンクセンター)
研究者・論文・化学物質などの科学系データを横断検索可能。
→ https://jglobal.jst.go.jp - 国立国会図書館オンライン
国内出版物の網羅的なデータベース。著者や出版情報の確認に便利。
→ https://ndlonline.ndl.go.jp - レファレンス協同データベース
全国の図書館が共有する「調べもの」の知識データベース。
→ https://crd.ndl.go.jp
まとめ
誤情報が拡散しやすい時代にあっては、情報の正確性と透明性が求められます。ファクトチェックは単なる確認作業ではなく、情報を発信する側と受ける側の信頼を築くための重要なプロセスです。
情報を発信する、情報を拡散する際には、以下の点に気を付けフェイクニュースに対処しましょう。
① 情報源の信頼性
・一次情報(公式発表・元資料)を確認しているか?
・情報の出典が明確に示されているか?
・不確かな噂や曖昧な情報をそのまま使っていないか?
② 根拠の提示
・使用したデータや統計、出典が明記されているか?
・情報の根拠が誰でも確認できる形で提示されているか?
・読者が納得できる透明性のある説明になっているか?
③ 情報の比較
・複数の信頼できる情報源(公的機関、専門メディアなど)を参照しているか?
・異なる立場や視点からの情報も含めて検討しているか?
・一部の情報や都合の良い情報だけを切り取っていないか?
④ 客観的な評価
・その分野に詳しい専門家の見解を取り入れているか?
・主観的な意見に偏らず、客観性を保っているか?
・利害関係のある発言者の意見を鵜呑みにしていないか?


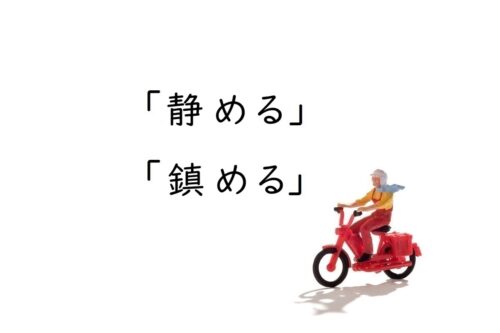






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Indentation-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)
