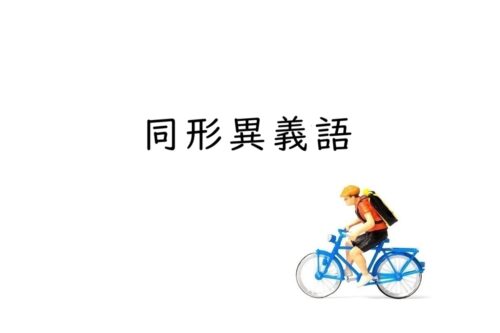目 次
やってはいけない!校正者が避けるべき5つのNGな行動
校正者は文章の誤りを見つけ、正確で読みやすい文章へと仕上げる重要な役割を担っています。しかし、どれほど経験を積んだ校正者でも、無意識のうちに「避けるべき行動」を取ってしまうことがあります。
校正のスキルを高めるためには、正しい校正技術を身につけるだけでなく、「やってはいけないNGな行動」を理解し、それを防ぐことが不可欠です。
この記事では、校正者が陥りがちなNG行動と、それぞれの回避策について紹介しています。
① 些細な部分にこだわりすぎる(全体の流れを見ない)
② 文脈を無視し、機械的に訂正する
③ すべての間違いを一度に見つけようとする
④ 曖昧な指摘をする(理由を明確にしない)
⑤ 過剰に指示を入れる(書き手の意図を考慮しない)
NGな行動①:些細な部分にこだわりすぎる(全体の流れを見ない)
文章の校正において、細かい部分にまで注意を払うことは非常に大切です。しかし、細かい部分ばかりを気にしすぎていると、文章全体の読みやすさや流れまで意識が向かないことがあります。
誤字脱字の訂正や表記統一だけに集中しすぎるあまり、結果として、文章全体のバランスがおかしくなり、読みやすさを損ないます。
たとえば、文章内の表記を何も考えずすべて統一しようとすると、書き手の文体や個性的な言い回しが失われてしまうことがあります。文章には書き手の意図やこだわりがあるため、細部に過度に手を加えると、元の文章の印象やリズムが失われてしまいます。
<NGな行動>
✖ 言い回しや「てにをは」、表記揺れなどの細部にばかりこだわりすぎる
→ 部分的な誤りばかりに気を取られていると、文章全体の確認が疎かになる。
✖ 文体や構成、リズムなど文章全体の流れを考慮しない
→ 文章の流れや一貫性を考慮しないで指示を入れると、文章がぎこちなくなり、不自然になることがある。
<適切な校正>
● 文章の概要を掴み、その後に細かい部分に目を向ける
→ まずは文章全体を読み、意味や流れを理解してから細部の確認に取り組む。
● 単語単位ではなく、文の流れや読みやすさを確認する
→ 校正後に文章を読み直し、全体として自然な流れになっているかをチェックする。
校正を行う際は、まず文章全体の流れや一貫性を確認し、その後に細部をチェックすることが重要です。細かいミスの修正も大切ですが、文章全体の流れを損なわないよう配慮する姿勢も必要です。校正の仕事では、常に「読みやすさ」や「伝わりやすさ」を意識し、俯瞰する視点を持ちながら作業を進めることを心がけましょう。
NGな行動②:文脈を無視し、機械的に訂正する
ルールやマニュアルに縛られすぎて、文脈を無視した訂正をしてしまうと、本来の文章の意味が変わってしまったり不自然な表現になってしまったりすることがあります。
言葉の使い方や表現の違いには、特に注意が必要です。たとえば、「ウェブサイト」「ホームページ」「トップページ」という言葉は、似た意味で使われることが多いですが、厳密にはそれぞれ異なる意味を持っています。「ウェブサイト」はインターネット上の一連のページ全体を指し、「ホームページ」はそのサイトの最初のページを指すことが一般的です。「トップページ」はホームページと似ていますが、特定のウェブサイト内の最上位ページを指すこともあります。このような違いを理解せず、単純に「表記の統一」として訂正を加えると、文章の意図が変わってしまう可能性があります。
また、現在では校正ソフトを導入している現場も多いですが、ソフトの指摘をそのまま適用することも危険です。校正ソフトは便利なツールですが、文章の意図やニュアンスを常に正しく理解できるとは限りません。指摘を鵜呑みにして訂正すると、かえって文章が不自然になったり、誤った修正をしてしまったりすることがあります。校正ソフトの指摘はあくまで参考とし、最終的な判断は自分で行うようにしましょう。
<NGな行動>
✖「ルールに従えば問題ない」と考え、機械的に訂正指示を入れる
→ 文章の意図や流れを考慮せず、単純にルールに従うだけの訂正をすると、読みづらい文章になることがある。
✖ 校正ソフトの指摘をそのまま鵜呑みにしてしまう
→ ソフトの指摘は必ずしも正しいとは限らないため、文脈に合わない修正をすると、文章の意味が変わってしまうことがある。
✖ すべての表記を統一しようとする
→ 文脈によっては異なる表記のほうが適切な場合もあるため、無理に統一すると、意味のズレが生じることがある。
<適切な校正>
● 文章全体の流れを確認する
→ 文章全体の意図や流れを把握した上で、適切な表現を選ぶ。
● 校正ソフトの指摘は参考程度にとどめる
→ 最終的な判断は自分で行う。
● 文脈に応じて適切な表記を選ぶ
→ 意味の似た言葉でも、文脈によって適切な表現がある。
●「読みやすさ」と「正確さ」のバランスを考える
→ ルールを守ることも重要だが、読みやすく自然な文章にすることも大切。
校正を行う際には、単純にルールに従うだけではなく、文章全体の意図や流れ、文体を意識する必要があります。それらを無視して機械的に訂正を加えると、かえって文章の質が低下してしまうことがあります。
校正ソフトを活用する際も、その指摘が本当に適切かどうかを自分で判断し、必要に応じて訂正指示を入れることが求められます。
NGな行動③:すべての間違いを一度に見つけようとする
校正には、さまざまなチェック項目があります。「文章の構成や整合性の確認」「誤字脱字のチェック」「文法の見直し」「表記の統一」など、それぞれ異なる視点からの確認が必要です。しかし、これらをすべて一度に行おうとすると、どうしても注意が分散し、結果として見落としが増えてしまいます。
これは、「マルチタスク」の弊害と同じです。人間の脳は、複数の作業を同時に処理するのが苦手です。たとえば、文章全体の流れをチェックしながら表記の揺れを見つけようとすると、どちらかに意識が偏り、もう一方の作業が疎かになってしまうことがあります。また、いろいろな要素に目を配るあまり、「読みやすく、正確な文章にする」という視点がぼやけてしまうこともあります。
このような問題を防ぐためには、作業の優先順位を決め、段階的に校正を進めることが重要です。まずは文章全体の構成を把握し、それから文法や表現のチェック、誤字脱字の確認へと進むことで、それぞれの作業項目に集中でき、より正確で効率的な校正ができるようになります。
<NGな行動>
✖ すべての作業項目を一度にチェックしようとする
→ 文章の構成や流れ、誤字脱字、文法、表記の統一などを同時に確認しようとすると、注意が分散し、かえって効率が悪くなる。
✖ 優先順位を決めずに作業を進める
→ どこから手をつけるべきかを決めずに作業を進めると、非効率になるばかりか品質にも影響を及ぼす。
✖ 途中で違う作業のほうに意識が移ってしまう
→ 文章の流れを確認している最中に他のことをしようとすると、本来の作業が中断され、集中力が散漫になる。
<適切な校正>
● 作業内容を整理し、「大枠→細部」という流れになるよう段取りを組み立てる
→ まずは文章の大きな構成を確認し、それから細かい部分へと進むことで効率的に作業ができる。(※「細部→大枠」でも構いません)
たとえば、次のような段階を踏んで作業を進めます。
1. 文章全体の構成と論理の整合性を確認する
2. 文法や表現のチェックを行う
3. 誤字脱字や表記統一、用語のチェックをする
4. 細かい体裁のミスなどを確認する
● チェックリストを作成し、段階的に作業を進める
→ やるべきことをリストアップし、一つずつクリアにしていく。
● 途中で気になったミスは、一旦メモして後で確認する
→ 文章全体の構成を見直しているときに何か気になる点があったときは、いったん鉛筆で丸印などをつけておき、後で見直す。
校正を行う際は、チェック項目をわけて段階的に作業を進めることで、より正確な作業が可能になります。「すべてのミスを一度に見つけようとしない」ことが大切です。やるべきことをメモなどにリストアップし、それを一つずつ潰していくのが賢明です。
「今は何を確認する段階なのか」を常に意識しながら作業を進めることで、それぞれのチェックに集中することができます。より正確な校正ができるだけでなく、効率化にもつながります。
NGな行動④:曖昧な指摘をする(理由を明確にしない)
訂正指示の内容が曖昧だと、修正を行う側がどのように直せばいいかわからず、迷ってしまうことがあります。
校正の指示は、「どこを、なぜ、どう直すべきか」を具体的に伝えることが大切です。単に文章の問題点を指摘するだけでなく、修正する側に指示内容を明確に伝えることが求められます。
また、指摘をする際には、できるだけ客観的な根拠を示すことも大切です。たとえば、「この単語は一般的には□□という意味で使われるため、ここでは△△としたほうが適切です」や「この表現だと、読者が□□と誤解する可能性があるため、△△としたほうが明確になります」といったように、修正の必要性が伝わるように補足を添えます。
指摘を的確に伝えるためには、「何が問題なのか」「どのように直せばよいのか」「なぜその修正が必要なのか」を明示することが大切です。具体的な例や代替案を示すことで、修正する側も理解しやすくなり、スムーズに作業を進めることができます。
<NGな行動>
次のような指示は具体性に欠け、修正する側にとってわかりづらいものになります。
✖「この部分、少し違和感があります。」(具体的な理由が不明確)
→ どのような点に違和感があるのかわからないため、修正の方向性が定まらない。
✖「もっと分かりやすくしてください。」(どこをどう直せばいいのか不明)
→ どの部分がわかりづらいのか、どうすれば改善できるのかが示されていないため、具体的な改善方法がわからない。
✖「この単語は別の表現にしたほうがいいかもしれません。」(どの表現が適切なのか具体例がない)
→ 替えるべき理由や、どんな表現が適しているのかが示されていないため判断に迷う。
<適切な校正>
● 指摘の際には理由と具体例を提示する
→ 例:「この表現では意味が伝わりづらいため、□□にするとわかりやすくなります。」
●「なぜ修正が必要なのか」を明確に伝える
→ 例:「この単語は専門用語のため、より一般的な□□にしたほうが、読者にとって理解しやすいです。」
● 客観的な根拠を示す
→ 例:「この言葉は一般的には□□という意味で使われるため、ここでは△△のほうが適切です。」
● 代替案を提示する
→ 例:「この部分の表現を〇〇に変更すると、より自然な文章になります。」
<より良い指摘のポイント>
・問題点を具体的に指摘する
→ どの単語や表現が問題なのかを明確に示す。
・修正の理由を説明する
→ なぜその修正が必要なのかを伝える。
・具体的な代替案を提示する
→ どのように修正すればよいのか方向性を示す。
・客観的な根拠を示す
→ 辞書や一般的なルールや用法をもとに指摘を行う。
校正での指摘は、単に「違和感がある」「わかりにくい」といった曖昧なものではなく、「どこを、なぜ、どのように修正すべきか」を具体的に示すことが重要です。明確に指示することで、修正する側がスムーズに内容を理解することができます。
また、指摘をする際には「客観的な根拠」を示すことで、その修正の必要性が増します。たとえば、言葉の意味や一般的な使用例を示したり、文法上のルールに基づいた説明を加えたりします。
そのためにも、「理由」と「具体的な改善案」をセットで伝えることが大切です。
NGな行動⑤:過剰に指示を入れる(書き手の意図を考慮しない)
校正においては、書き手の意図や文章の背景を考慮せずに過剰に手を加えることは避ける必要があります。校正者として文章の誤りや改善点を指摘することは大切ですが、必要以上に指示を入れてしまうと、書き手の個性や表現を損なうことになります。
文章の文体や表現には書き手の個性が反映されています。たとえば、小説やエッセイのような創作的な文章では、意図的に砕けた表現や独特のリズムを用いている場合があります。そのような表現を「一般的な書き方」に統一しようとすると、文章の持つ魅力や個性が失われてしまうことがあります。
校正者は、あくまでサポート役であり、主役は書き手であることを忘れないようにしましょう。
<NGな行動>
✖ 書き手の文体や独自の表現に配慮せず、一般的な表現に直そうとする
→ 文章の持ち味を損ない、書き手の個性が損なわれる。
✖ 意味が通じるのに、必要以上に文章を整えようとする
→ 校正の本来の目的から逸れる。
✖ 誤りではない部分にまで指示を入れすぎる
→ 文章の訂正箇所が増えすぎて、書き手が混乱する。
✖ 書き手にとって重要な表現であることを考慮せず、「ルール」を優先してしまう
→ 書き手の意図やメッセージが正しく伝わらなくなる。
<適切な校正>
● 書き手の意図を考慮し「本当に訂正が必要か?」を判断する。
→ 書き手の文体や表現を尊重し、修正が必要な場合のみ指摘をする。
● 文章のオリジナリティを守り、意味が通じる部分は不用意に変えない。
→ 書き手の個性や表現のこだわりを損なう指摘は避ける。
● 文章の流れや意図を損なわないよう、最小限の訂正にとどめる
→ 不要な指示を避け、可能な限り原文を活かすよう心がける。
校正は「正確性を期す」仕事であって、添削や改変ではありません。書き手の文体や表現のこだわりを尊重し、最小限の修正にとどめることが大切です。
また「過剰な指示になっていないか?」を常に意識し、不必要な指摘を避けることも重要です。
おわりに
校正者は、文章の質を向上させる役割を持ちますが、書き手の意図を尊重し、適切な距離感を持って校正を行い、作業の精度を高めることが重要です。そのためには、技術を磨くだけでなくNGな行動を理解し、改善し続ける姿勢が求められます。
周りから信頼される校正者になるには、正しい校正技術を身につけるだけでなく、「やってはいけないNGな行動」を理解し、それを防ぐことが不可欠です。
校正は一人で完結するものではなく、書き手やクライアント、他の校正者などとの共同作業です。独りよがりの校正を避け、周囲との協調を大切にしながら、より高いレベルの校正を目指しましょう。


![校訂(こうてい)とは何か?どんな作業をする?[校訂の意味と役割]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/03/Meaning-of-Revision-500x333.jpg)

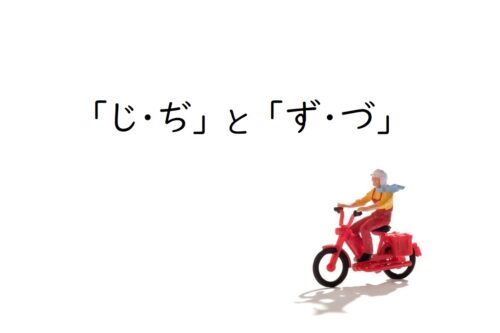
![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)
![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)
![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)