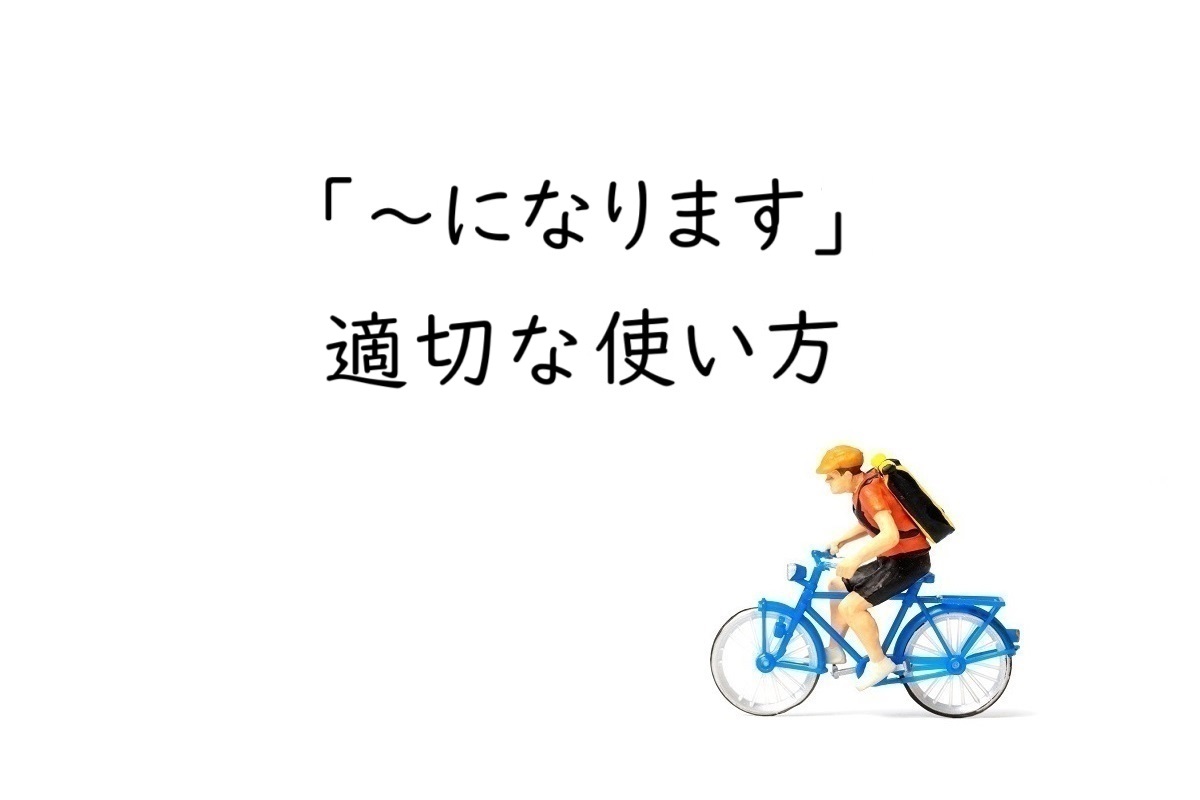
目 次
「~になります」の適切な使い方とポイント【いい例・悪い例】
「〜になります」は会話でも文章でもよく使用される表現です。丁寧な響きがあるため、つい使ってしまいがちですが、「~になります」には適切な使い方と不自然な使い方が存在します。
どんな場面で「〜になります」を使うのが適切なのか?
この記事では、「〜になります」の本来の意味や正しい使い方、よくある誤用例や注意点についてわかりやすく解説します。
[記事作成にあたっては、以下の書籍・辞書・サイトを参考にしています]
・『デジタル大辞泉』(小学館)
・『新明解国語辞典 第八版』(三省堂)
・『広辞苑 第七版』(岩波書店)
・『敬語の指針』(文化庁)
1.「~になります」の本来の意味
「~になります」は「~になる」の丁寧語で、「〜に変わる/〜という状態に移行する」という変化を意味します。文法的には「〜に+なります(動詞)」という形で、動作や状態の変化をやわらかく伝える効果があります。
「~になります」が持つニュアンス
・ある状態が別の状態へ推移する
・ある判断や計算・経過を通じて、最終的に何かに落ち着く
・結果としてその状態に到達することを表す
▼ 本来の意味に当てはめて「~になります」を使用した場合
『4月から社会人になります』というと、「4月から(学生という身分から)社会人に変わる」と解釈できます。一方、『こちらが説明書になります』という場合、「こちらが説明書に変化する」という不自然な意味になってしまいます。
2.「~になります」の適切な使用場面
文法的に「~になります」の適切な使用は次のような場面です。
① 状態の変化
・明日は晴れになります。(曇りから晴れへの変化)
・水を加熱するとお湯になります。(水からお湯への変化)
② 計算・判断の結果
・ご注文は合計で5,000円になります。(計算の結果)
・審査の結果、合格になります。(判断の結果)
③ 役職・立場の変更
・来月から部長になります。(役職の変化)
④ 予定・決定の変更
・このまま議論が進むとA案になります。(状況の推移)
3.「~になります」の不適切な使用例
次に「~になります」のよくある誤用例を紹介します。間違いの大半は「変化が伴わないもの」に対して使ってしまうケースです。
「~になります」の不適切な例文
・こちらが当社の新製品になります。
・この商品の特徴は耐久性になります。
・こちらが本日のランチメニューになります。
・私がここの担当者になります。
「~になります」はやさしい響きで丁寧に聞こえるかもしれませんが、厳密に言えば不適切となるケースがあります。
4.「~になります」の言い換え
変化が伴わない単なる説明・断定では「~になります」でなく、「~です」やさらに丁寧な「~でございます」で言い換えることができます。
「です」で言い換え
・こちらが当社の新製品です。
・この商品の特徴は耐久性です。
・こちらが本日のランチメニューです。
・私がここの担当者です。
「ございます」で言い換え
・こちらが当社の新製品でございます。
・この商品の特徴は耐久性でございます。
・こちらが本日のランチメニューでございます。
・私がここの担当者でございます。
おわりに
「~になります」は、状態の変化や結果を表す丁寧語です。説明や断定の文では「~です」や「~でございます」の使用がしっくりくることも多いです。
ただ、「〜になります」は文法的に微妙であっても、コミュニケーションにおいては柔らかくやさしい印象を与えやすいというメリットがあります。
相手に丁寧さを伝えたい気持ちから「正確さ」よりも「印象」を優先した結果として、「〜になります」という表現が使用されることも多いです。このような背景を考慮すれば、説明や断定の文でなくても「〜になります」の使用が許容とされるケースは多いでしょう。

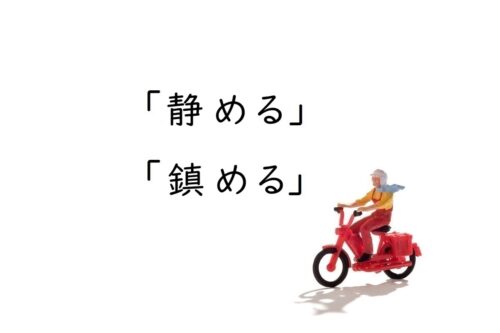






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)
![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![一字下げる・一字下げにしない[校正記号の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/indent-in-proofreading-mark-500x334.jpg)
![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)
