
目 次
国立国会図書館を賢く活用!利用方法からデジタルコレクションの情報検索まで紹介】
校正の調べ物において、インターネットは欠かせない存在になっています。とはいえ、インターネット上の情報は断片的だったり信憑性に欠けていたりする場合もあり、書籍に当たった方が確実かつ早いこともあります。そんなときに活用したいのが、国立国会図書館(以下、国会図書館)です。
日本国内で発行されたすべての出版物は、国会図書館に納入することが義務づけられています。国会図書館にはそうして収集された資料が、小説や実用書はもちろん、専門書、漫画、雑誌、新聞、地図や楽譜まで、約4800万点所蔵されています(2024年度時点)。
国会図書館は東京本館(東京都千代田区)、関西館(京都府相楽郡)、国際子ども図書館(東京都台東区)の3つの施設からなりますが、この記事では東京本館と、オンラインで利用できる「国立国会図書館デジタルコレクション」(以下、デジタルコレクション)について解説します。

■ 国立国会図書館(東京本館)>https://www.ndl.go.jp/
■ 国立国会図書館デジタルコレクション >https://dl.ndl.go.jp/
■ 国立国会図書館(関西館)>https://www.ndl.go.jp/jp/kansai/index.html
■ 国立国会図書館(国際子ども図書館)>https://www.kodomo.go.jp/
1. 国立国会図書館 東京本館の利用方法

■ 国立国会図書館 > https://www.ndl.go.jp
① 利用者登録
東京本館をはじめとする国会図書館の利用には、利用者登録が必要です。満18歳以上であれば誰でも登録することができます。
なお、入館するだけであれば、カウンターで申し込みをすると当日のみ有効な入館カードを発行してもらえます。しかし、大半の資料の閲覧やコピーなどには利用者登録が必要なので、校正の仕事として国会図書館を利用する際には登録することになるでしょう。
登録手続きは直接来館して行うほか、オンラインと郵送でも可能です。ただし、オンラインと郵送の場合は手続きに日数がかかり、即日の利用はできません。
② 利用の流れ
■ 入館について
利用者登録をするとICカードが発行されます。入館の際は、このカードを入り口のゲートにタッチします。カードは入館してからも資料の閲覧申し込み・受け取り、コピーの申し込み・受け取りなどあちこちで使うので、取り出しやすいようにしておくのがおすすめです。
なお館内には、B5判以上の不透明な袋物(かばんや紙袋など)は持ち込めません。そのため、荷物はゲートの外にあるコインロッカーに預けることになります。コインロッカーの利用料金は利用後に返却されますが、ロッカーの中身を取り出す際には一度ゲートを出なければなりません。利用中の資料がある間はゲートを出られないので、必要なものまでロッカーに入れてしまわないように気をつけましょう。
筆記用具や貴重品など館内に持ち込むものは、備え付けのビニールバッグに入れます。ちなみにこの備え付けのバッグは、以前は持ち手のないビニール袋で、正直なところ使い勝手はよくありませんでした。しかし2022年ごろから、持ち手つきのしっかりしたビニールバッグに変更され、使いやすくなっています。
■ 資料の閲覧について
国会図書館の大きな特徴は、一般の図書館のように利用者が直接資料を取り出すのではなく、利用申し込みをして出してもらうシステムを取っていることです。
利用申し込みの手続きはオンラインになっており、流れは以下の通りです。
① 館内のパソコンや自分のスマートフォンなどで「国立国会図書館サーチ」(https://ndlsearch.ndl.go.jp/)にアクセス
② 閲覧したい資料を検索
③ 資料が見つかったら申込カートに入れる
④ 画面の指示に従って閲覧を申し込む
⑤ 館内のパソコンや自分のスマートフォンなどで状況を確認し、カウンターに到着したら受け取りに行く
申し込みから到着までの時間は混雑状況によって変動しますが、10分から30分ほどかかると思っておくとよいでしょう。また、館内のパソコンが埋まっていてなかなか空席が見つけられず、閲覧申し込みに時間がかかることもあります。
手際よく利用するには、来館前に準備をしておくとよいです。③の申込カートに入れるところまでは館外からでも可能なので、事前にカートに入れておき、入館したらすぐにスマートフォンなど自分の端末で閲覧を申し込むようにすると時間の短縮になります。
上記で説明した閲覧の流れは、書籍などの原本を閲覧できる資料の場合です。一部の資料はデジタル化されており、原本ではなくデジタル画像を館内のパソコンから閲覧することになります。これがデジタルコレクションで、後ほど詳しく解説します。
■ 資料のコピーについて
国会図書館では資料のコピーもセルフではなく、申し込みをしてコピーしてもらう形になっています。
閲覧申し込みをして手元にある資料については、館内のパソコンとプリンターで「複写申込書」を出力することができます。そこにコピーを希望するページを記入し、あわせて資料の該当箇所に備え付けの紙のしおりを挟んで、複写カウンターに提出します。
コピーを申し込む際に気をつけなければならないのは、著作権保護の観点から、コピーできる範囲に制限があることです。たとえば単行本なら1冊の半分まで、論文集ならそれぞれの論文の半分までというように規定されています。希望のコピー範囲が規定を超えていた場合、複写カウンターで規定内に収めるよう指示されるので、本当に必要なポイントのみに絞って申請し直すなどの対応が必要になります。
コピーにかかる時間も混雑状況によって異なり、5分程度で完了することもありますが、30分以上かかることもあります。待ち時間の目安は複写カウンター付近にリアルタイムで表示されているので、時間配分に気をつけて計画的に利用しましょう。
■ 退館について
入館時と同様、ゲートにカードをタッチして退館します。利用中の資料や受け取っていないコピーがあると退館できないので注意が必要です。
2. 国立国会図書館デジタルコレクションの利用方法

■ 国立国会図書館デジタルコレクション > https://dl.ndl.go.jp/
① 概要
ここまで東京本館について説明してきましたが、地方在住であったり締め切りまでの時間がなかったりして、直接来館することが難しい場合もあるでしょう。そんなときに便利なのがデジタルコレクションです。
国会図書館では2000年度から所蔵資料のデジタル化を進めていましたが、2021年度からさらに力を入れており、2024年度時点で約446万点がデジタル化されています。所蔵資料の1割弱がデジタル化されている計算です。
デジタルコレクションの公開範囲は、以下の3段階に分かれています。
① インターネット公開:インターネット上に公開されており、原則として国会図書館の利用者登録をしていなくても閲覧できる。
② 図書館・個人送信対象:国会図書館の利用者登録をしていれば、自宅のパソコンなどから閲覧できる。
③ 国立国会図書館内限定:国会図書館の館内でのみ閲覧できる。
2024年度時点では、① インターネット公開:約65万点、② 図書館・個人送信対象:約204万点、③ 国立国会図書館内限定:約177万点となっています。
①と②の合計約269万点が、来館しなくても自宅のパソコンなどから見られるということです。ここには著作権保護期間が満了した古い資料や、絶版などのため手に入れるのが難しい資料も含まれています。調べ物において強力なツールになるでしょう。
ちなみに、デジタル化の具体的な作業内容については、『国立国会図書館月報』で紹介されています(https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_12233022_po_geppo2205.pdf?contentNo=1#page=8)。大変などという表現では生ぬるい、気が遠くなるような作業に頭が下がります。
② 利用方法
来館しなくても閲覧できる資料は、国立国会図書館サーチの検索画面で絞り込むことができます。「インターネットで閲覧できるものに絞る」をオンにすると、上記の①②に該当する資料に絞って表示されます。
デジタルコレクションの素晴らしい点は、その多くの本文がOCR(光学文字認識)処理によってテキスト化されていることです。つまり本文内検索が可能なのです。
校正者であれば、ゲラ上に出典の書名は示されているもののページまでは記載されておらず、1冊丸ごと目を通さなければならないのか……?と絶望した経験があるでしょう。そんなときでもデジタルコレクションであれば、キーワードで検索することで該当箇所にたどり着きやすくなります。
デジタルコレクションの資料は、自宅などのプリンターでも印刷することができます。ただし、利用者IDと氏名、印刷日時が印字されるため、資料として提出する際に気になるようであれば、個人情報部分を塗りつぶすなどの手間がかかります。
おわりに
以上、国会図書館の利用方法について解説しました。
近年では事実確認(ファクトチェック)の範囲について「インターネットで調べられる範囲で」と依頼されることも多くなっていますが、デジタルコレクションを活用できると、インターネットで調べられる内容の幅が広がります。まだ使ったことのない方は、ぜひ一度触れてみてください。

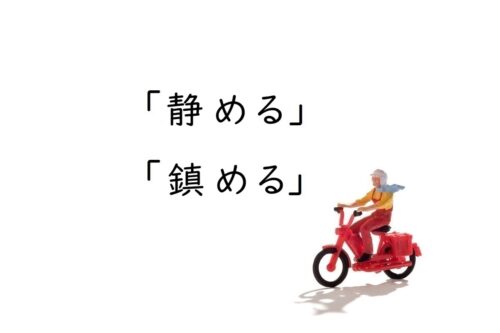






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)
![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![一字下げる・一字下げにしない[校正記号の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/indent-in-proofreading-mark-500x334.jpg)
![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)
