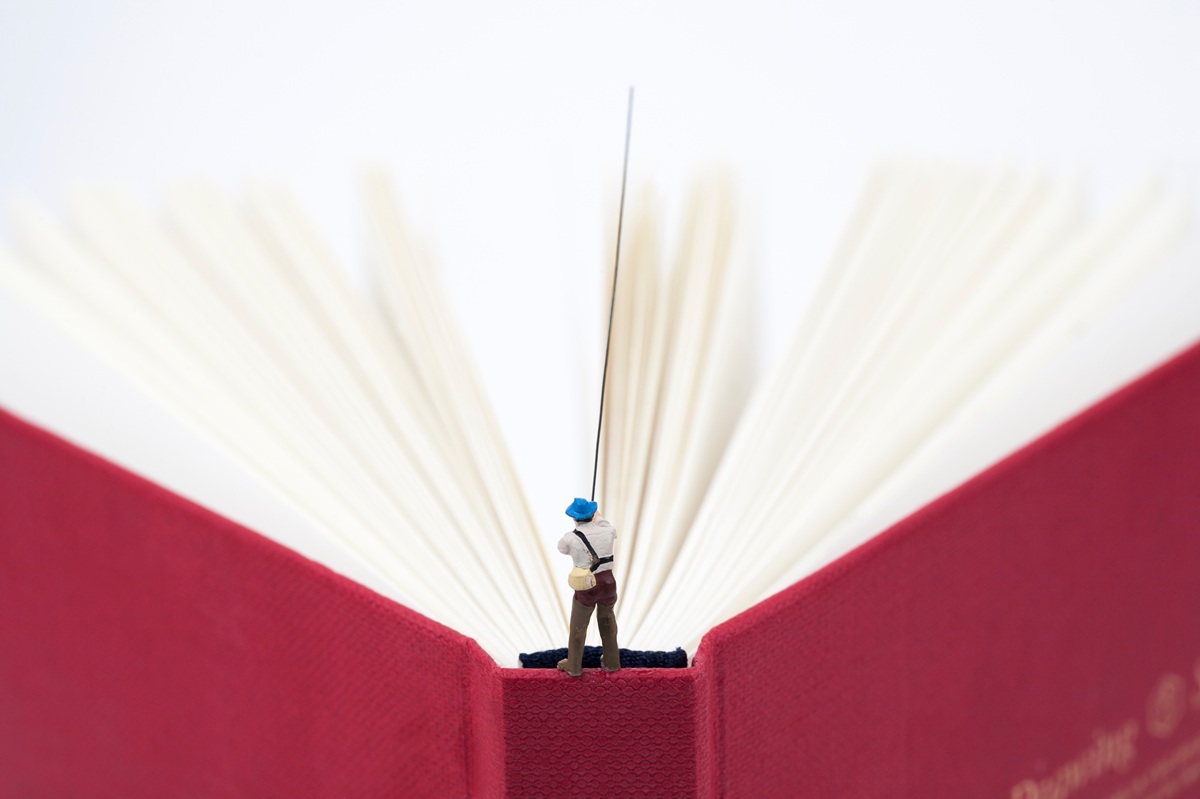
目 次
すぐに役立つ!校正で失敗しない3つの視点「鳥の目・虫の目・魚の目」
校正の仕事には、どれだけ経験を積んでも大切にすべき「3つの目」があります。
それが「鳥の目」「虫の目」「魚の目」です。これらは、視点を切り替えることの大切さを示す言葉として、校正以外の仕事でもよく使われます。この3つの言葉を知らなくても、ベテランの校正者の多くは無意識に実践している見方でもあります。
この記事では、文章の校正において「鳥の目・虫の目・魚の目」をどのように使って間違いを見つけていくのかを具体的に紹介していきます。

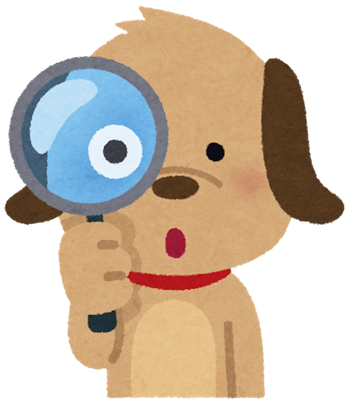
1.「鳥の目」で文章を見る
鳥の目 … 空から全体を眺める視点
鳥が空から地上を見渡すように、文章全体の構成や話の流れを「俯瞰」してチェックするのが「鳥の目」です。文章の細かい部分にとらわれず、大きな視野で確認します。
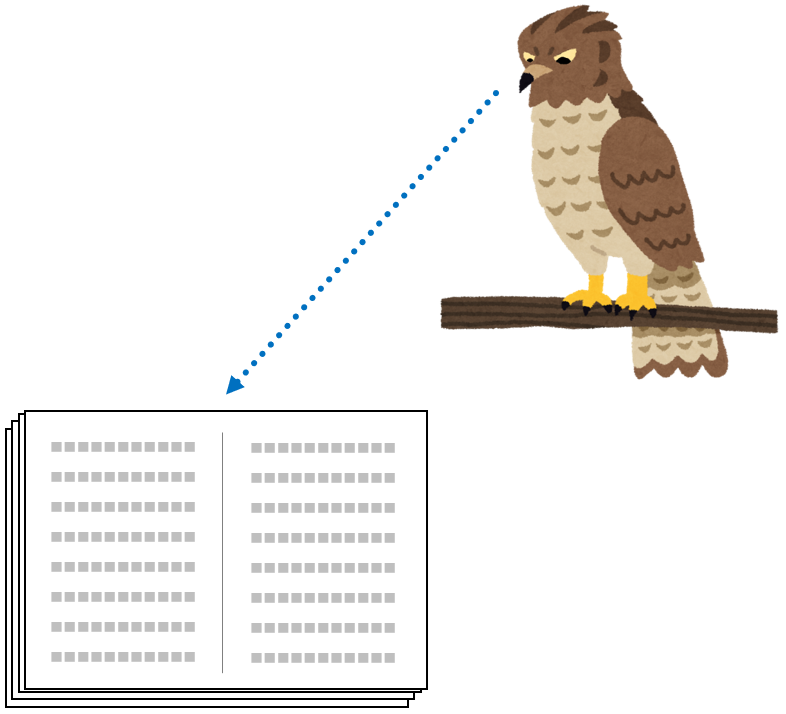
「鳥の目」の主なチェックポイント
🔵 テーマや主張は一貫しているか?
・タイトルと本文の内容がちゃんと一致しているか。
・最初に掲げた主張と本文中の内容、結論までが矛盾なくつながっているか。
【例】文章のタイトルが『AIの活用法を徹底解説』なのに、内容はAIの特徴や将来性についてばかり述べている。
🔵 見出しや項目の並び順は適切か?
・各見出しの配置が論理的で理解しやすい順番か。
【例】見出し「1. 準備」→「2. 手順」→「3. 注意点」→「4. まとめ」のように順序立てて説明されているか。
🔵 文章全体の流れや構成は論理的でわかりやすいか? 情報に過不足がないか?
・話題が急に飛んだり、前提となる説明や根拠が抜けていないか。
・関係性のない情報や読み手に不要な情報が混じっていないか。
【例】「AはBです。だからDです」というように、本来入れるべき「C」の説明が抜けている。
🔵 同じ内容の重複はないか?
・一度説明したことを表現を変えて繰り返して説明していないか。
【例】「AI校正のメリット」と「AI校正の特長」といったように似たような見出しで同じ内容が書かれている。
鳥の目で文章のどこまで確認するかに正解はありませんが、一つの基準としては、作業時間で区切ったり作業単位で区切ったりして、自分が納得のいくレベル感で線引きするとよいでしょう。自分に合ったやり方を見つけ、ストレスなく校正をする際のルーチンワークとするのが最善です。
また「鳥の目」の作業中に細かいミスを偶然見つけてしまった場合は、鉛筆で丸をしておき、後で対処しやすいようにしておくとよいです。間違いを見つけた際に、逐一赤字を入れても問題ないですが、「今は鳥の目で俯瞰して文章を見ている」ことを意識して作業が脱線しないように注意しましょう。
2.「虫の目」で文章を見る
虫の目 … 細部をじっくり観察する視点
虫が地面を這いながら小さなものを見ているように、言葉の一つひとつや文字単位にまで視点をフォーカスさせ、文法、誤字脱字、表記ミスなど文章の「細部」を入念にチェックするのが「虫の目」です。
「虫の目」は、文章の読みやすさや正確さに直結する最も基本的な視点です。校正・校閲といえばこの「虫の目」がイメージされることが多いです。

「虫の目」の主なチェックポイント
🔵 誤字脱字はないか?
・誤変換、スペルミスがないか。
【例】✕「鑑賞に老ける」→ ○「感傷にふける」
🔵 助詞や助動詞などは正しく使われているか?
・「は」「が」「を」など、意味を正確に伝えるための助詞・助動詞が適切か。
【例】✕「犬が散歩に行く」→ ○「犬と散歩に行く」
🔵 数字・固有名詞は正確か?
・金額、日付、企業名、人名、商品名などに誤りがないか。
・単位(kg、%、円など)の表記ミスがないか。
🔵 表記揺れ(表現の統一)はないか?
・同じ意味の語句や用語が文章全体で統一されているか。
・カタカナや略語、アルファベット表記が一貫して使用されているか。
【例】「ウェブ」と「Web」、「子ども」と「子供」
🔵 接続詞の使い方は正しいか?
・「そして」「しかし」「また」「けれども」「そのため」など不適切なつなぎ方になっていないか。
🔵 二重表現(重複表現)は含まれていないか?
・「まず最初に」「頭痛が痛い」など、不自然な重複がないか。
🔵 文末や敬語表現は統一されているか?
・「です・ます」調と「だ・である」調が混在していないか、敬語が乱れていないかもチェックする。
【例】「この商品はおすすめです。さらに、高性能である。」
以上のような、さらっと文章を見ただけではわからないような間違いを「虫の目」で探していきます。「鳥の目」で文章全体の構成や筋道をチェックし、「虫の目」で誤字脱字や表現の細かなミスを丁寧に確認することで、これまで見えてこなかった間違いを見つけられる可能性が高まります。
3.「魚の目」で文章を見る
魚の目 … 時代の流れを読む視点
「魚の目」とは、魚が川の流れを敏感に感じ取って泳ぐように、時代の流れや世の中の動きを的確に捉える視点のことです。校正では、文章が現代の社会や読者の感覚に合っているか、その価値観からズレていないかをチェックするのが「魚の目」です。
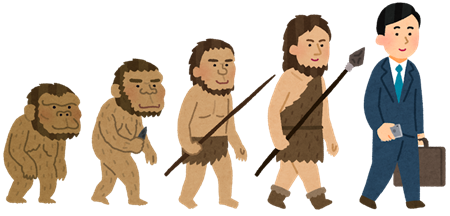
「魚の目」の主なチェックポイント
🔵 読者層に合った内容・言葉を選んでいるか?
・年齢層や属性に対して、文章表現、漢字、専門用語を使用していないか。
【例】子ども向けの文章なのに、難しい表現や漢字が使われていないか。
🔵 情報やデータは最新か、信頼できる情報か?
・古い統計情報、情報源不明のデータを引用していないか。
・参照元・出典がきちんと記載されているか。
🔵 時代や社会の価値観にそぐわない表現や不適切な表現がないか?
・差別的・偏見的な表現や、性別・年齢・職業に関する旧来表現がないか。
・特定の人種、属性などを一括りにして断定したり、ネガティブなイメージを植え付ける表現を使っていないか。
・時代遅れになった言葉や、読者層にそぐわない言葉が使われていないか。
【例1】「男だから機械に強い」「若者は軽薄な行動をとる」などの断定表現がないか。
【例2】「看護婦」→「看護師」、「保母さん」→「保育士」など、現代に合った呼称や言い回しに修正されているか。
この「魚の目」は特定の段階で使うのではなく、常に持ち続けるべき土台となる視点です。「鳥の目」では全体を「虫の目」では細部を詰めていきますが、「魚の目」は文章作成の始めから終わりまで常に持ち続ける視点です。
この「魚の目」の視点が抜けていた場合、文章の内容が読者の感覚にそぐわないことになりかねません。その結果、途中で読むのをやめられてしまうという悲しい結果につながります。
おわりに
校正というと「虫の目」を重視しがちですが、全体を俯瞰する「鳥の目」や、読者に配慮する「魚の目」も大切な視点です。どんなに経験を重ねても、この「3つの目」を忘れずに校正に取り組むことで、校正者として文章の品質を支える役割を担い続けることができるでしょう。
<まとめ>
鳥の目 = 文章全体の構成や流れ、骨組みをチェック
虫の目 = 誤字・脱字、表現の誤りなど細部をチェック
魚の目 = 読者層に見合った内容か、表現内容の鮮度や時代性をチェック

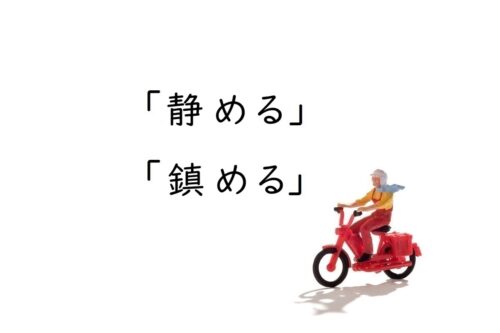






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Indentation-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)
