![いい校正者とはどういう人?[適性やスキルだけでは測れない要素]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Who-is-the-good-proofreader.jpg)
目 次
いい校正者とはどういう人?[適性やスキルだけでは測れない要素]
いい校正者とされる要素は色々と考えられます。
- 経験年数が長い
- 携わった媒体が豊富
- スキルが高い
- 頭がいい
- 知識が豊富
このようなことがパッと思い浮かぶかもしれませんが、どれが一番かを決めることはできません。
その基準は、各校正者や校正の媒体、企業によって様々だからです。
- 色々な媒体を扱う校正現場なら対応力のある人、経験値の高い人
- 広く一般的な教養が必要なら総合的な知識を備えた人
- 特定のジャンルに特化した媒体なら、その分野での専門的な知識がある人
などが要求されます。
また特徴にまで絞ればキリがありません。
- 粘り強い人
- 読解力のある人
- 飲み込みの早い人 etc.
そのため、ここでは一般的に広く当てはまるような、いい校正者とはこういう人ではないかを考えてみました。あくまで一校正者の考えなので、これから校正の道に進まれる方はこういう考え方もあるんだなという程度でご覧ください。
結論から言うと、
いい校正者とは、安定した品質を保てる人だと考えています。
安定した品質を保つのには、ある程度のスキルが必要になってきますが、スキルが高いからといって品質が安定しているというわけではありません。スキルが高くても品質にムラのある人は結構います。
※品質にムラが起こる原因は、一概に校正者個人のせいとは言えません。職場環境に左右されることもあります。
安定した品質を保てる人が選ばれるわけ
「品質」や「安定」など抽象的な言葉が続くので、校正の仕事に就いていない方はいまいちピンとこないかもしれません。以下、例で示すのでイメージだけでもつかんでください。
▼ピンチの場面での投手の起用
投手Aは、
球速がある、球種も多い。
でも、球がすっぽ抜けることがしばしばある。
制球にやや難がある。
投手Bは、
投手Aよりも球速は劣り、球種も少ない。
でも、球がすっぽ抜けることが少ない。
制球が安定している。
両投手を起用する場面は、状況によって違ってくると思います。
試合の序盤なら、その日の調子を見てどちらの投手を起用するかを判断すると思います。ですが、9回裏ランナー3塁、一打逆転といった緊迫した場面では、どちらの投手にすべきかより慎重になって悩むはずです。
投手Aを起用して球がすっぽ抜けて暴投で試合が終わってしまうより、制球に安定感のある投手Bを手堅く起用したほうが、可能性として暴投で試合が終わる確率を下げることができます。その分だけ勝率が上がるということになります。
たとえのせいで逆にわかりにくくなったかもしれませんが、
校正は常にミスと隣り合わせの仕事です。いつも9回裏でランナーを背負っている場面に近い状態と言えます。リスクのある場面では、品質がより安定した人のほうが選ばれる傾向にあります。
端的に言うと、100点を取らなくてもその代わり60点も取らない、常に80点をキープできる校正者が、いい校正者というイメージです。
いい校正者として除外できる要素
以下のようなことは、いい校正者の要素とされる場面もありますが、近い将来除外されるかもしれません。
1. スピード
校正をするスピードが速いことは、いい校正者の要素とは言い難いです。スピードがあることは当然いいことですが、それほど重要なことではありません。
スピードがなくても、納期の調整や校正期間の交渉をするなど、校正以外の努力で何とかなるからです。
一日にこれだけの量をこなさないといけないからスピードが何よりも重要だ!という場合は、スケジュール管理の仕方を間違っているか、スキルを安売りしている可能性があります。自ら量をこなさないといけない状態にしてしまっているということです。
2. 専門知識
校正においては、現在では専門知識を持っていることは圧倒的に有利ですが、将来的なことを考えれば有利かどうかは疑問です。特定の分野に特化させたデジタル校正支援は進歩しています。AIの進歩も凄まじいものがあります。今後、専門知識は、頭の中に詰め込むよりもデータに蓄積してゆくほうが賢明と言えるかもしれません。
現在では人にアドバンテージがあっても、将来的にはいい校正者としての要素となりえるか判断が難しいところです。
品質の安定は、安心感を与える
校正の仕事を依頼する人・校正の仕事を割り振りする人にとっては、
品質の安定している校正者が重宝されます。
依頼する立場からすれば、安心して仕事を任せられるからです。
仕事を丸々任せられなくても、この仕事のこの部分は、この校正者に任せれば何とかなるという場合も同じです。
安心して仕事を任せられるということは、依頼する側からすれば、頭の中からそのタスクを完全に切り離すことができ、他のタスクに集中して取り掛かれることができます。
品質が安定してる → ブレが少ない → 仕上がりの精度が見込める → 計画が立てやすい
このループが安心感につながっていきます。
また品質が安定することで、やり直し(再チェック)も減り、負荷が減ることも考えられます。
複数の校正者と仕事をしている方なら、ご自身の周りにも品質が安定している校正者はいると思います。経験年数が浅くても、スキルが高くなくても、この仕事なら(もしくはこの部分なら)この人に任せとけば安心という校正者です。
品質の安定は、才能か努力か?
安定した品質を保てる人は、漠然と仕事をしながら品質をキープしているわけではありません。それなりの努力をしています。
集中力や持続力を高めるために、適度な休憩やストレッチ、糖分補給など実践しています。忙しいときでも、目の前の仕事に振り回されず、自分なりのルーチンを維持していることも多いです。
たとえば、午後3時になったら一旦休憩をとったり、90分に一度は身体を伸ばすストレッチをしたりするなどごく簡単なことです。他にも仕事の前日には夜更かしをしない(十分な睡眠をとる)、お昼ご飯は腹八分目ですませる(食べすぎると眠気がくるので)といった形で、何らかの工夫をしています。ただ単に何も意識せず品質が安定しているというわけではありません。
当然、体調が悪い日も無理をしません。体調が悪いときは自分ではできていると思っていても頭が回らず、聞き間違い・書き間違いなど些細なミスを起こしてしまうことをよく理解しています。
いい校正者は「頭が少し痛いんですけど薬を飲んだから大丈夫です。頑張ります」などとは言いません。
それでもやらざるを得ないときは、
- いつもより見るスピードを落としてゆっくり見る
- 見直しの回数を増やす
- ややこしいところは別の校正者にダブルチェックをお願いする
など自分の体調を考慮して慎重に仕事に取り組みます。
要するに、
品質が安定している人は、自分の能力をよく理解していて過信しません。
来た仕事を安請け合いすることもないです。適度な距離間をもって校正という仕事に真摯に取り組んでいます。
自分には集中力や持続力がないので難しいかも……と感じた人もいるかもしれませんが、品質の安定は才能などでなく自分の力で何とかできるものです。
周りにお手本となるような校正者の方がいるなら、観察してみると勉強になると思います。
校正の仕事においては、スキルアップだけが品質を支えるものではないということがわかると思います。知識よりも仕事に取り組む姿勢がいかに大切か学べるはずです。
Below is the English version of the article.
Who is the good proofreader?
There are many elements to be good proofreaders as below;
• Many years of experience.
• Plenty of experience that they worked for various media.
• Great skills.
In general, you will probably come up with something like the above but it is still hard to decide which one is the best.
The reason is that criteria depend on proofreaders, media that they work for, or companies.
They require some factors like below;
• Clients who deal with multiple types of media need proofreaders that can work flexibly or having a lot of experience.
• If clients need general education/culture, proofreaders who have plenty of knowledge in various fields are suitable.
• Some who have particular knowledge in a certain industry are suitable for corresponding categories of media.
Also, features of ideal proofreaders are such as;
• Patient.
• Excellent comprehension skills for reading.
• Quick learner.
There are still some other factors but I cannot list everything right here.
Thus, I will demonstrate essential elements to be good proofreaders, who generally fit in this industry from the next section.
This is just my personal opinion so that I want you to know that some proofreaders who work in this industry might think like this.
Straightforwardly, I think good proofreaders are some who can retain the stable quality of their work.
It is necessary to have a certain level of skill set to keep the excellent quality but it does not mean high skilled proofreaders always maintain the solid standard.
In other words, there are also some proofreaders who have great skill but unbalanced quality.
Proofreading is a job that always contains the risk to make a mistake. Thus, clients tend to hire proofreaders who have stable skills and quality if it is a risky situation.
Ultimately, the client does not expect its outcome to be perfect but neither un-matured level. Great proofreaders always retain good standards.
*What causes unstable quality is not necessarily because of individuals. It might be affected by the working environment.
What I list below can be factors to be good proofreaders but might be unnecessary in the near future.
1. Speed
We cannot say proofreading speed is the core factor to be a great proofreader. In fact, it is nice if you can work quickly but not necessarily that much.
Even if you cannot work speedily, you can also manage it by doing something else such as adjusting the schedule and negotiating the proofreading period.
If speed is the most important for you because you have to finish a certain amount of work in a day, it means you had a mistake in scheduling or sold your skill at a cheap price. In that sense, you can improve the situation by yourself.
2. Expert knowledge
It is quite an advantage if you have knowledge in a particular field when it comes to proofreading. However, it is also controversial whether if it is an essential skill in the future. As you know, digital proofreading software for some industries has been progressing. Thus, you had better store knowledge as data rather than memorize them.
Even if humans have an advantage at this moment, the situation might be changed in the future.
Stable quality gives a sense of security
For clients who need proofreading, ideal candidates must have stable quality.
The reason is stable quality gives a sense of security for them.
Likewise, clients can assign a part of the entire task to proofreaders.
In that case, clients delegate tasks for proofreaders and focus on their own work.
The routine of working with good proofreaders is like below;
Stable quality → avoid random mistakes → predict the level of the final version → it helps them to make accurate plans/schedule
This routine gives security to clients.
In addition, stable quality reduces resubmission and burden.
If you work with multiple numbers of proofreaders, you might see someone who has solid quality. Those proofreaders have trust from their clients even if their experience is not long or do not have high skills.
What does make quality stable? Is it talent or effort?
Good proofreaders do not keep their stable quality without strategies. They do a lot of effort such as taking appropriate break time, stretch exercise, replenishing sugar for the brain. Even if they are busy, they retain their own routine without being bothered by the work they face to.
For example, easy actions such as taking break time at 3 in the afternoon every day, doing the stretch exercise once in 90 minutes help them to keep good quality of work.
Besides, they try to maintain themselves in a good condition by doing actions such as;
• Do not stay up until late midnight (it means they sleep enough)
• Do not eat that much, you should try eating until you're 80 percent full (because eating too much makes them sleepy)
In short, good proofreaders have their own strategies to retain quality.
No need to say, they do not overdo when they feel unwell. They understand well that they might have a mistake or miswrite when their brain cannot focus on work.
Therefore, they would not say like “I have a headache but I am fine because I took medicine.”
If they have to work under hard circumstances, they try these tips below;
• Check carefully with a slower speed than usual.
• Increase number of re-check.
• Ask other proofreaders to double-check, particularly for the complicated part.
With these strategies, they care for themselves and try to work on it.
In a conclusion, good proofreaders understand their competencies well and do not overestimate themselves. Consequently, they do not take work without thinking carefully. They try to perceive themselves objectively and work sincerely.
Some of you might think you do not have enough concentration or sustainability but you can try to get stable quality with your effort, not talent.
If you know someone who is a good proofreader, you might as well observe well and learn from them. You will understand that skill-up is not the only element that retains good quality. At the same time, it is clear that attitude tackling their work is significantly important.

![文章の校正:5つの基本的な見方[文字に意識を集中させるコツ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/Basic-Text-Proofreading-Techniques-500x342.jpg)
![文章校正の実力テスト[校正力UPの練習問題]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/text-proofreading-exercises-500x338.jpg)
![【伝わる指示 vs 伝わらない指示】良くない校正指示と改善ポイント[いい校正者になる第一歩]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/good-and-bad-proofreading-instructions-500x333.jpg)

![[校正の落とし穴]正しい修正が新たな間違いを生む?! 連鎖する間違いを止める](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Chain-of-proofreading-mistakes-500x333.jpg)
![校正記号をクイズで学ぶ![校正記号の基礎から応用まで勉強]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Learn-proofreading-symbols-through-quizzes-500x334.jpg)
![文章校正記号:この記号の意味は?[イラストから記号の意味を逆引き検索]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-proofreading-symbol-in-prooreading-500x333.jpg)
![校正の依頼メールで押さえておきたいポイント[例文あり]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Email-request-for-proofreading-500x362.jpg)
![文章校正ではなぜ一文字ずつ確認する必要があるのか?[タイポグリセミアが原因⁉]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/01/typoglycemia-in-proofreading-500x258.jpg)
![AIに文章の校正を依頼する[無料で使えるAI校正ツールの比較]一番使えるAIは?](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Free-AI-Proofreading-Tools-500x330.jpg)
![原稿との突き合わせ校正(引き合わせ校正)の実技解説[校正の基本のやり方を紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/08/Demonstration-of-proofreading-techniques-500x333.jpg)
![校正のパタパタ(あおり校正)のやり方[動画で解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/05/Proofreading-Technology-500x333.jpg)
![広告・出版・マスコミ業界で働くならマスメディアンで仕事探し[特長や強み・利用の流れの紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/04/find-a-job-with-MASSMEDIAN-500x333.jpg)
![校正者になるには[未経験者へ仕事内容から資格・求人まで解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/How-to-Become-a-Proofreader-500x333.jpg)
![大阪で校正会社や校正者を探す[どこに仕事を依頼する?どこに求人を出す?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/07/Proofreading-company-500x333.jpg)
![差し替えと差し換え:どっちの表記が正しい?[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-replacement-and-replace-in-proofreading-500x333.jpg)
![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)
![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![「広がる」と「拡がる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/10/Spreads-and-Expands-500x333.jpg)
![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)
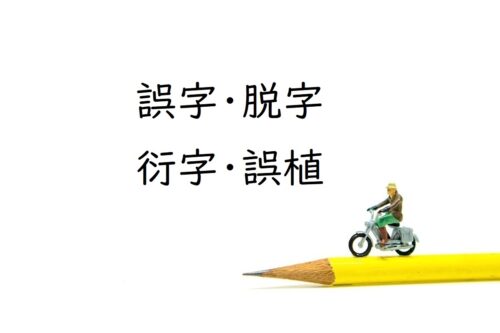
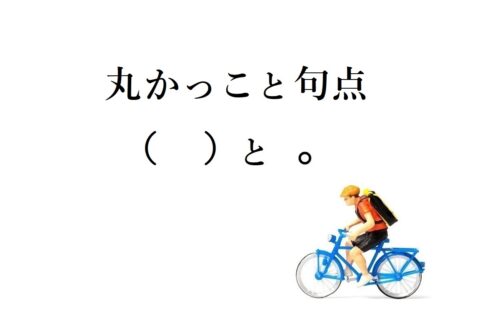
![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)
![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)
