![校正・校閲のミスをなくすためにすべきこと[漢字の使い分けや用法]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/09/eliminate-proofreading-error.jpg)
校正・校閲のミスをなくすためにすべきこと[漢字の使い分けや用法]
漢字の使い分けや用法は、膨大でかつ多様なため、いち校正者がすべてを覚えきるのはほぼ不可能です。しかし、校正者は、常に間違いを見つけなくてはならない過酷な立場にいます。
その膨大な情報のどこから手を付けるべきかを考えたら途方に暮れるかもしれませんが、やるべきことは決まっています。
まずは身近に起こった間違いから着実に潰していくことです。起こる可能性の高いミスから優先的に頭に叩き込み、起こる可能性の低いものは優先度を下げます。
市販の書籍などで、漢字の使い分けや用法などを学習するのは後回しで大丈夫です。
校正する媒体によって、使う漢字も表現も違ってきます。ジャンルによっては、ある程度用語もカテゴライズされます。やみくもに学習するのは効果的とは言えません。
たとえば、ファッション雑誌に携わる校正者が、約款などに使われる漢字や表現を覚えたところで、その使用頻度は低いので実務に役立つかどうか疑問です。
そのためにも、知識やノウハウの蓄積・共有は必須になってきます。
校正の現場に則した勉強材料
実際に自分の周りで起こった誤変換や漢字の使い分けなどを蓄積したものから、ランダムに抜粋したものを以下にまとめてみました。
自分の制作環境にとっては役立つものばかりです。新人研修などにも活用できるため効果は大きいです。
実際に起こった間違いの蓄積
実際にデータとして間違いを蓄積する際は、以下の項目も必要に応じて記載しておくと後々役立ちます。
・日付
・間違いが発生した媒体名
・間違えた原因や対策
蓄積の際は、Wordなどで文章形式にするのではなく、Excelで蓄積していくことをおすすめします。なるべく、1セル・1メッセージにするよう心がけます。そうしておくと、デジタル校正ソフトなどに単語登録する際に便利になります。
<読み方が同じで混同されやすいもの>
| 蓄 ・ 畜 | 蓄圧式~ |
| 郡 ・ 群 | 住所で使うのは「郡」 |
| 縁 ・ 緑 | 広縁~ |
| 躯 ・ 駆 | 躯体~ |
| 複 ・ 復 | 複層ガラス~ |
| 会 ・ 界 | ○○工業会が「界」になっていた |
| 板 ・ 版 | メラミン化粧板~ |
| 國 ・ 国 | 「柳田国男」と入っていた。人物名はいわゆる旧字体も多い。 |
<字形が似ている漢字>
| 賃 ・ 貸 | 見間違えしやすい文字 |
| 径 ・ 経 | 見間違えしやすい文字 |
| 間口 ・ 開口 | 見間違えしやすい文字 |
| 保温 ・ 保湿 | 見間違えしやすい文字 |
| 若手 ・ 苦手 | 見間違えしやすい文字 |
<誤変換されやすく、混同されやすいもの>
| 仕様 ・ 使用 | 誤変換しやすい文字 |
| 動線 ・ 導線 | 誤変換しやすい文字 |
| 持って ・ 以て | 誤変換しやすい文字 |
| 日本初 ・ 日本発 | 誤変換しやすい文字 |
<よく出てくる同音異義語の使い分け>
| 追求 ・ 追及 | 「追求」は追い求める、「追及」は追いつめる |
| 実績 ・ 実積 | 「実績」は積み重ねられた業績、「実積」は実際に測った面積 |
| 伺う ・ 窺う | 「伺う」は聞く・問う・訪ねる、「窺う」は探る・察する・待つ |
| 気密 ・ 機密 | 「気密」は気体を通さぬこと、「機密」は政治・軍事上の大切な秘密 |
| 侵入 ・ 浸入 | 「侵入」は不法に入ること、「浸入」は水が入ること |
| 滅菌 ・ 減菌 | 「滅菌」の所に「減菌」と入っていた。よく似た字なので注意。 |
| 観賞 ・ 鑑賞 | 「観賞」は見て楽しむこと。(例:観賞植物、観賞魚) 「鑑賞」は芸術作品を理解し、味わうこと。(例:名画を鑑賞する) |
| 粗い ・ 荒い | 「粗い」は大まか・ざらざら、 「荒い」はげしい・荒々しい・甚だしい・ごつごつ。 「あらびき」は「粗」の方 |
| 傷める ・ 痛める | 「傷める」は破損、「痛める」は痛苦 |
| 偽装 ・ 偽造 | 「食品偽造」と入っていた。 |
| 店舗 ・ 店鋪 | 「鋪」は旧字体 |
| 人口 ・ 人工 | 人口○○万人~ |
| 渾身 ・ 懇親 | シェフ渾身の~ |
| 消火 ・ 消化 | 消火設備~、消化器官~ |
| 化学 ・ 科学 | 化学繊維~ |
| 賞品 ・ 商品 | 賞品の当選者の発表は~ |
| 短辺 ・ 短編 | 短辺側○○mm~ |
| 出展 ・ 出典 | イベントに「出展」と引用文章の「出典」 |
| 偲ぶ ・ 忍ぶ | 「思いが忍ばれる」というような誤用があった。 「忍」は耐え忍ぶときに使用。 |
| 確率 ・ 確立 | 可能性についていうときは「確率」 |
| 褒章 ・ 褒賞 | 勲章(紫綬褒章)のしょうの字が「賞」に |
| 受章 ・ 授章 | もらったので「受」章のはずが、さずける方の「授」章に |
| 良く ・ よく | 良し悪しの意味での使用は、良く。 頻度を表す場合は、よく。 |
| 標準形/形式 ・ 標準型/型式 | 「型」と「形」はよく混同される字。 |
| ギ(「示」+「氏」) 祗 | 祇園の「祇」の字は「示」+「氏」または「ネ」+「氏」。 「氏」の下にヨコ棒がついた「祗」は別の字。 |
以上はほんの一例ですが、社内で起こった間違いを日々蓄積した結果です。
蓄積した間違いを系統によってカテゴライズすることで、頭の中で整理でき覚えやすくなります。
分類は、間違いの系統でなく、校正する媒体ごとでも大丈夫です。
まとめたものを校正者間で共有することは当然ですが、制作サイドとも共有することで社内全体の品質向上が見込めます。場合によっては、クライアントと共有することもあります。
校正者だけでできることは限られてきます。他の職種と連携して、いかにミスの削減に取り組んでいくかが大切です。地道な活動ですが、品質向上に必ず貢献します。
知識は効率のよい学習で吸収する
校正の実務的な技術は基礎から学んでいくのが効果的ですが、知識的なことはいかに効率よく覚えていくかが大切です。漢字の使い分けや用法は、一生掛かっても覚えきれるものではありません。
そのためには、まず以下のことから取り組んでいくことです。
・自分が校正していて、実際に起こった間違いを蓄積する
・実際に起こった間違いから、他にも同じような間違いがないか考える
・自分が携わる校正物をパラパラと捲ってみて、間違えそうなものがないか推測してみる
間違いを蓄積する基準としては、『次にその間違いが起こった場合、誰もが見つけることができるか』の視点で情報を残しておくことです。
不要だと思う情報は極力取り除きます。情報としていろいろと残したくなりますが、通常業務の負担にならないようにすることが大切です。
負担になると、やがて蓄積すること自体が面倒になってきて、どこかで自然消滅してしまいます。そうなると、本来の目的を見失いかねません。最初のカギは、いかに通常業務にスムーズに組み込んでいけるかです。




![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)
![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
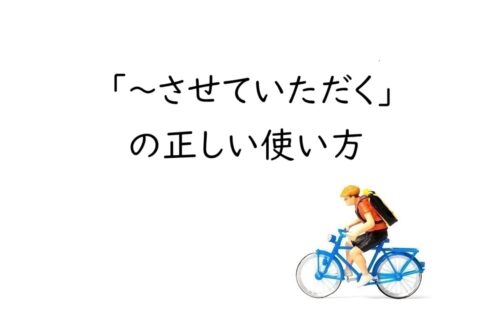

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)


