
目 次
校正のミス防止対策である「ダブルチェック」は『リンゲルマン効果』で無意味なものになる
「リンゲルマン効果」とは、集団で作業を行うと、一人ひとりの作業効率や努力が低下する現象をいいます。簡単に言うと、人数が増えるほど一人あたりの「やる気」や「努力」が低下するということです。
この現象は「社会的手抜き」とも呼ばれ、集団での作業は、責任の分散が起こりやすく、また個人の貢献が見えにくくなる傾向があるとされています。『自分一人が頑張らなくてもいい』『他の人が頑張るから自分は少し手を抜いても大丈夫』という考えに陥ったり、自分の努力が全体の成果にあまり影響しないと感じたりする心理が原因とされます。
このような現象をフランスの農学者リンゲルマンが実験で確認したことから、「リンゲルマン効果」と呼ばれています。
この「リンゲルマン効果」が、校正の「ダブルチェック」とどういう繋がりがあるのか。
1. ミスの背景にある思い込み
どんなに優秀で注意深い人でも、校正の仕事においては見落としを起こします。見落としには、知識や経験不足からくるミス、疲労によるケアレスミス、環境要因によって引き起こされるミスなどさまざまな原因がありますが、中には「思い込み」が影響するミスもあります。
思考に偏りがあると、自分では意識せずとも校正作業に反映されてしまいます。
校正においては以下のような思い込みが考えられます。
「これだけ時間をかけたのだから大丈夫だろう」
「何度も読み直したから問題ないだろう」
「こんなに赤字を入れたから、もう他に間違いはないだろう」
「この文章は優秀なライターさんが書いたものだから誤字は少ないはずだ」
「この赤字修正はベテランのオペレータさんがやったから修正間違いは少ないはずだ」
「過去の間違いの傾向から、この辺りにだけ注意していればいい」 など
また、思い込みは文章の読解力不足や、校正時間がなく焦ってしまい勘違いするといった状況からくることもあります。他にも、過去に見落とした間違いや、これまでの経験則から無意識のうちに思い込みが刷り込まれているケースもあります。良くも悪くも何らかの思い込みを誰もが持つものです。
2. 思い込みが原因のミスへの対処
校正の仕事において、思い込みを軽減する方法として、効果的でよく知られているのが時間を置くことです。
校正作業後に時間を置くことで、注意対象への思い込みが薄れ、再度見直した際に気づけなかった間違いにも気づきやすくなります。時間を置いて、後から冷静になって考えてみて「なんでこんなことに気づけなかったんだろう」といったことは誰もが経験していると思います。時間が経てば記憶が薄れていくように、思い込みも薄れていきます。
あまり時間を取れない場合は、校正作業後に別の作業を入れて、その後に見直しをする方法もあります。他の仕事を間に挟むことで、他の仕事のほうに一旦意識が行くので、前の仕事への思い込みが薄まります。この方法は実践している方も多いかもしれません。
校正支援ソフトやAIの校正ツールなどを導入するのも思い込みをなくすのに有効です。機械的にチェックするため人の思い込みが入る余地がありません。
ただ現段階では、ソフトやツールに依存しすぎるのも危険です。どんなに優れた校正ソフトであってもすべての間違いを指摘してくれることはありません。また、AIであれば学習した情報に影響されることもあるので適切でない結果が返ってくることがあります。頼れる部分は大いにありますが、まだ安心できるものではありません。
他にも、思い込みからくる間違いへの対策として、ダブルチェックも有効な手段の一つです。同じ内容を異なる人の視点からチェックすることで、客観性が向上するため、自分では気づけなかったミスに気づいてもらえる可能性が高くなります。
ダブルチェックは、校正だけでなく様々な現場で実践されています。実際に、企業や出版社などでは、ダブルチェックが標準的なルールとして採用されていることは多いです。
このダブルチェックはミス防止の有効な手段の一つですが、心理的な落とし穴も潜んでいます。そこで重要になるのが冒頭で紹介した『リンゲルマン効果』です。
3. ダブルチェックは『リンゲルマン効果』によって無意味なものとなる
先にも述べたように、複数人が同じ作業をしていると、個人の責任が薄れ、「自分がやらなくても他の人がやってくれるだろう」という考えに陥ってしまうことがあります。この心理により積極的なチェック行動が減少し、確認が疎かになります。こういった考えが集団内に蔓延すると、結果として重大なミスが見逃されることになります。
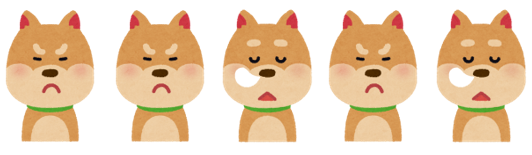
リンゲルマン効果の影響を校正のダブルチェックに当てはめた場合、間違いを見つけようという意識、注意力、集中力、粘り強さに影響してきます。
また校正という作業は、校正者だけが行うものではなく他の職種の方々も行います。たとえば、クライアントや著者、デザイナー、編集者、ライターなどです。
たくさんの人が目にするものほど、無意識に心理的な甘えが生じ、注意が疎かになったり気の緩みにつながったりします。
たとえば、表紙や背表紙、裏表紙などの誰の目にもよく触れるところは、一部が間違っていても誰も気づかないことがよくあります。最終工程になってミスが発覚することも珍しくありません。
有名なところでいうと、漫画『ドラゴンボール』の単行本を並べて背表紙の絵をつなげると、ドラゴンボールを持った神龍を追いかける各キャラクターの絵ができあがります。17~19巻の背表紙には、ヤジロベーが出てきますが、25~27巻の背表紙にもヤジロベーが再度登場します。これは作者のミスらしく、読者のお便りで発覚したそうです。
このような事例も、関与者側の立場になれば、「誰もが見ているだろう」「そんな間違いを起こすはずがない」という理由から、個々の注意力が低下するリンゲルマン効果が働いていたのかもしれません。
4. 校正での『リンゲルマン効果』への対策
ミスが多いからといって、ダブルチェック、トリプルチェックと単に人数を増やすだけで精度が上がるわけではありません。普通に考えると、確認する人数が多ければ品質が上がるように思えますが、実際はその逆で、全体のパフォーマンスを低下させてしてしまうことがあります。
このリンゲルマン効果の対処法としては、一般的に個人の責任感を希薄にさせない、明確な役割分担をすることなどがあげられます。
校正においての対策は次のようなものが考えられます。
① 意識改善
どんなに優れたシステムでも運用側の意識が低ければ、無用の長物となります。同様に、個々の意識が低ければ、どのような手段を用いても結果は同じです。
リンゲルマン効果は、経験から学ぶ問題ではなく意識の問題です。知っているか知っていないかが重要になってきます。そのため、この現象を回避するには、問題をしっかりと認識し、知識として持っているかどうかが重要になってきます。
リンゲルマン効果は、集団の中で無意識に行ってしまう行動に由来するため、まずはこの問題を顕在化させ、意識的に取り組む必要があります。このような現象が起こり得るということを常に念頭に置いて、集団での作業に臨むことが大切です。
具体的には、次のような点を各自が意識するようにしましょう。
・どこかにほころびが生じていないか?
→ 作業やプロセスの中で、小さなミスや見落としが発生していないか。
・形骸化している工程がないか?
→ 本来の目的が見失われて、ただ形式的に行われているだけの工程がないか。
・周りに頼りすぎていないか?
→ 他のメンバーに依存しすぎて、自分の責任を怠っていないか。
こうした点を意識することで、各自が自分の役割をしっかりと認識し、「他の人がやってくれるだろう」という心理的な甘えを防ぐことができます。
② 校正後の署名
チェック後に誰が確認したのかを記録しておくのも効果的です。たいていの校正の現場では、誰がいつやった仕事かをわかるように何らかの形で残しているはずです。
校正をした際に、自分が確認したというサインを残すのはごく普通のことですが、サインを書く場所は、校正ゲラ(校正紙)の下のほうに小さく書いておくのが理想です。
別のシートに記入する方法でも問題ありませんが、自分が確認したゲラに作業者である自分の手で、自分の名前をサインすることで責任感を高めます。誰が校正したのかゲラを見て一目瞭然であることは責任の所在を明確にします。
これはダブルチェックにおいても同様です。ダブルチェックは補助的な作業でなく、確立した作業であることを明示するため、ダブルチェックをしたというサインを残すことで仕事に対する責任感を高めます。
③ 集団の結束力を強める
ミーティングや勉強会を繰り返し行うことは、集団のメンバー同士の結束力を高めるために非常に重要です。結束力を強化することで、個々のメンバーが集団に対する帰属意識をより強く感じるようになります。これにより、自分自身がグループの一員として存在しているという意識が生まれ、それに伴い責任感も自然に育まれてきます。
さらに、こうした取り組みがうまく機能すれば、一人ひとりの生産性が通常以上に向上するようになります。「リンゲルマン効果」とは逆の現象を引き起こすことが期待できます。
このように、集団の活動を通じて結束力を高めることは、個人のやる気や能力を引き出し、全体の成果向上に繋がっていきます。
④ チェックリストの活用
チェックリストは、どの作業が完了しているのか、何がまだ残っているのかを明確にするために役立ちます。チェックリストを活用することで、手抜き作業から起こる「作業の抜け漏れ」を防ぐことができます。
ただし、単に「チェックをした」という形式的な確認作業になってしまうと意味がありません。リンゲルマン効果への根本的な対策としては、①で述べた「意識改善」が優先になってきます。
おわりに
校正に限らず、関与者が多い場合、「リンゲルマン効果」が及ぼすリスクを理解しておく必要があります。ミスを減らすには、関与する人たちの意識や責任感が大きな役割を果たします。
集団での作業では「責任の分散」が生じやすく、これが「社会的手抜き」の原因となります。そのため、個人が自分の役割を明確に理解し、責任を持って取り組むことが大切です。一人ひとりが当事者意識を持つことがミス防止に大きく貢献します。
確認作業においては、「責任感の希薄化」や「他者への依存」など、人的要因で起こるミスも多くあります。ミス防止には、デジタル化といった技術面だけでなく、人的要因にも配慮し人と技術のバランスの取れた取り組みを行いましょう。
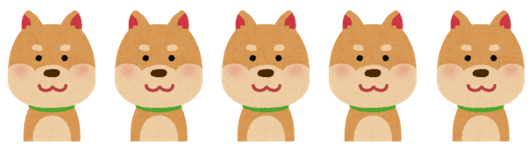

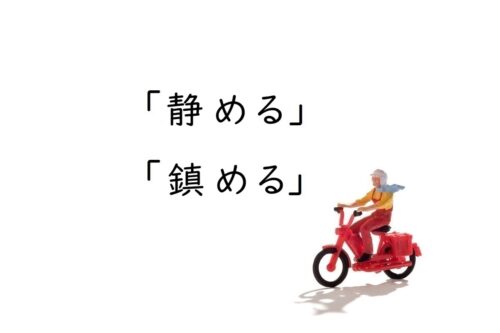






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)
![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

