
目 次
- 面倒でもスッキリ!日本語の微妙な言葉の使い分けを知る
- ①「〜に際して」と「〜に当たって」
- ②「〜に基づいて」と「〜に準じて」
- ③「〜によっては」と「〜によれば」
- ④「〜に沿って」と「〜に④従って」
- ⑤「〜とともに」と「〜にともなって」
- ⑥「〜のもとで」と「〜のもとに」
- ⑦「〜において」と「〜で」
- ⑧「〜として」と「〜にして」
- ⑨「〜としては」と「〜にしては」
- ⑩「〜を通じて」と「〜を通して」
- ⑪「〜に限り」と「〜に限って」
- ⑫「〜がち」と「〜やすい」
- ⑬「〜ついでに」と「〜がてら」
- ⑭「〜さえ」と「〜すら」
- ⑮「〜向け」と「〜用」
- ⑯「〜しか」と「〜だけ」
- ⑰「〜きり」と「〜だけ」
- ⑱「〜ばかり」と「〜だけ」
- ⑲「〜といえば」と「〜といったら」
- ⑳「〜ものの」と「〜とはいえ」
- おわりに
面倒でもスッキリ!日本語の微妙な言葉の使い分けを知る
日本語には一見すると意味が同じようで、微妙に違う表現が多く存在します。たとえば、「〜によれば」と「〜によると」、「~さえ」と「~すら」などです。
このような表現を何となくの感覚で使い分けている方も多いかもしれません。ただ、うっかり使い方を間違えてしまうと、読み手に誤解や違和感を引き起こしかねません。
この記事では、微妙に意味が異なる表現について使い分けのポイントを紹介します。
[記事作成にあたっては、以下の書籍・辞書・サイトを参考にしています]
・『新明解国語辞典 第八版』(三省堂)
・『広辞苑 第七版』(岩波書店)
・『明鏡国語辞典 第二版』(大修館書店)
①「〜に際して」と「〜に当たって」
<共通点>
「〜に際して」と「〜に当たって」はどちらも、何かを始めるときやある機会に使う表現です。
<違い>
■「〜に際して」は、特別な出来事や公式な場面など、改まった場面で使います。
例文:面接に際して、スーツの着用をお願いします。
■「〜に当たって」は、何かを始めるときの準備や注意点を述べるときに使います。
例文:新しい仕事を始めるに当たって、マニュアルを見直しました。
ポイント:「〜に際して」は特別な出来事や機会に使い、「〜に当たって」は準備や心構えを示すときに使います。
②「〜に基づいて」と「〜に準じて」
<共通点>
「〜に基づいて」と「〜に準じて」はいずれも、何かを根拠や基準として行動するときに使う言葉です。
<違い>
■「〜に基づいて」は、法律や規則といった厳密な基準をもとにして行動するときに使います。
例文:社内規定に基づいて行動してください。
■「〜に準じて」は、ある基準をおおよそ参考にし、必要に応じて調整する場合に使います。
例文:先輩のやり方に準じて行動しました。
ポイント:「〜に基づいて」は厳密な基準に従う場合に、「〜に準じて」は状況に合わせて柔軟に対応するときに使います。
③「〜によっては」と「〜によれば」
<共通点>
「〜によっては」と「〜によれば」は二つとも、条件や根拠を示すときに使います。
<違い>
■「〜によっては」は、条件によって結果が変わる場合に使います。
例文:天気によっては、今日の試合は中止です。
■「〜によれば」は、情報源や根拠を示すときに使います。
例文:ニュースによれば、明日は雨だそうです。
ポイント:「〜によっては」は状況による違いを、「〜によれば」は情報源であることを表します。
④「〜に沿って」と「〜に④従って」
<共通点>
「〜に沿って」と「〜に従って」はどちらも、方針や基準に合わせて行うことを表します。
<違い>
■「〜に沿って」は、何らかの方針やガイドラインに合わせて行動する場合に使います。
例文:この手順に沿って作業してください。
■「〜に従って」は、命令や指示、規則に従う場合に使用します。
例文:決められたルールに従って行動してください。
ポイント:「〜に沿って」は方向や指針に合わせるイメージで、「〜に従って」は命令や指示に服従するイメージです。
⑤「〜とともに」と「〜にともなって」
<共通点>
「〜とともに」と「〜にともなって」はいずれも、複数のことが一緒に起こるときに使います。
<違い>
■「〜とともに」は、ほぼ同じタイミングで二つのことが起こる場合に使います。
例文:春とともに暖かくなります。
■「〜にともなって」は、一つのことに合わせて他のことも起こる場合に使います。
例文:成長にともなって責任も増えます
ポイント:「~とともに」は同時進行を、「~にともなって」は何かに付随する変化や影響を強調するときに使用します。
⑥「〜のもとで」と「〜のもとに」
<共通点>
「〜のもとで」と「〜のもとに」は二つとも、誰かや何かの影響下で行動するときに使います。
<違い>
■「〜のもとで」は、人や指導者の指導や影響下で用います。
例文:プロの音楽家のもとでピアノを習っています。
■「〜のもとに」は、条件や理念など抽象的なものの下で何かを行うときに使います。
例文:安全第一のもとに、行事が行われました。
ポイント:「~のもとで」は人物や指導者の下、「~のもとに」は条件・理念・状況の下という意味で使い分けます。
⑦「〜において」と「〜で」
<共通点>
「〜において」と「〜で」は両方とも、場所・場面・時間を示すときに使います。
<違い>
■「〜において」は改まった場面や書き言葉で使われ、場面や時間など幅広く使えます。
例文:現代社会において、コミュニケーション能力は重要です。
■「〜で」は、日常的でくだけた場面でよく使われ、「~において」と同様、頻繁に使用される言葉です。
例文:今日は図書館で勉強します。
ポイント:「~において」はフォーマル・文語的、「~で」はカジュアル・口語的として使い分けます。
⑧「〜として」と「〜にして」
<共通点>
「〜として」と「〜にして」はどちらも、立場や役割を表すときに使います。
<違い>
■「〜として」は、その立場や役割を自然に述べる場合に使います。
例文:私は委員長として発表します。
■「〜にして」は、その立場であっても例外的なことや特別なことを強調するときに使います。
例文:ベテランの校正者にしてこんなミスをするなんて……。
ポイント:「~として」は立場の明示に、「~にして」はその立場であるにもかかわらずといった強調や意外性に使います。
⑨「〜としては」と「〜にしては」
<共通点>
「〜としては」と「〜にしては」はいずれも、立場や属性にもとづく評価や比較に使います。
<違い>
■「〜としては」は、そのグループや立場での一般的な評価に使います。
例文:校正初心者としてはよくできています。
■「〜にしては」は、予想と違う意外な評価をするときに使います。
例文:初めてにしてはよくできています。
ポイント:「~としては」は立場に応じた一般的な評価を、「~にしては」は予想基準との差を評価する表現です。
⑩「〜を通じて」と「〜を通して」
<共通点>
「〜を通じて」と「〜を通して」は二つとも、手段や経路、期間を表します。
<違い>
■「〜を通じて」は長い期間や抽象的な手段に使います。
例文:一年を通じて努力しました。
■「〜を通して」は具体的な方法や経路に使います。
例文:指示は上長を通して伝えてください。
ポイント:「〜を通じて」は長期や抽象的な内容、「〜を通して」は具体的な方法や経路を強調します。
⑪「〜に限り」と「〜に限って」
<共通点>
「〜に限り」と「〜に限って」は両方とも、何かを限定する意味の言葉です。
<違い>
■「〜に限り」は、公式に適用範囲を決めるときに使います。
例文:小・中学生に限り割引がききます。
■「〜に限って」は、特別な場合や例外の出来事に対して使います。
例文:今日に限って傘を忘れた。
ポイント:「〜に限り」は公式な範囲限定、「〜に限って」は偶然の例外・特別な場合を示します。
⑫「〜がち」と「〜やすい」
<共通点>
「〜がち」と「〜やすい」はどちらも、そうなりやすい傾向を表します。
<違い>
■「〜がち」は、個人や物の癖やパターンを示します。
例文:最近、遅刻しがちなので注意しましょう。
■「〜やすい」は、もともとの性質や構造からそうなる場合に使います。
例文:この素材は燃えやすいです。
ポイント:「〜がち」は習慣や癖、「〜やすい」はもとの性質や構造によりそうなる場合を表します。
⑬「〜ついでに」と「〜がてら」
<共通点>
「〜ついでに」と「〜がてら」はいずれも、何かの機会を利用して別のことをする表現です。
<違い>
■「〜ついでに」は、主な用事をしながら、他の用事もする場合に使います。
例文:コンビニに行くついでに手紙を出します。
■「〜がてら」は、主な行動をしながらそれに付随して別の行動も行うという意味です。「ついでに」よりも両方の行動の重要性が均等に近い印象があります。
例文:買い物がてら街の様子を見てきました。
ポイント:「〜ついでに」は主従関係があり、「〜がてら」は両方の行動を並列して行う印象が強い表現です。
⑭「〜さえ」と「〜すら」
<共通点>
「〜さえ」と「〜すら」は二つとも、極端な例や最小限・意外な例をあげて強調する表現です。
<違い>
■「〜さえ」は、日常会話や親しみやすい文章に使います。
例文:簡単な問題さえ分かりませんでした。
■「〜すら」は、書き言葉やフォーマルな文で、より強い強調や深刻さを出したいときに使います。
例文:彼は水すら飲もうとしませんでした。
ポイント:「~さえ」は口語的な強調表現で「それだけでも十分」という意味を含み、「~すら」は文語的でより強い驚きや深刻さを表し「それまでも」という意味を持ちます。
⑮「〜向け」と「〜用」
<共通点>
「〜向け」と「〜用」は両方とも、対象や用途を示します。
<違い>
■「〜向け」は、は対象となる人や集団を示します。
例文:校正初心者向けのテキストです。
■「〜用」は、具体的な使用目的や機能を示します。
例文:製図用のペンを買いました。
ポイント:「〜向け」は人の対象、「〜用」は使い道を示す表現です。
⑯「〜しか」と「〜だけ」
<共通点>
「〜しか」と「〜だけ」はどちらも、制限や限定を表す語です。
<違い>
■「〜しか」は、否定形と一緒に使い、他にないことを強く表します。
例文:もう200円しか残っていません。
■「〜だけ」は、肯定でも否定でも使え、範囲や数量の限定を表します。
例文:水だけ買いました。
ポイント:「~しか」は否定専用の強い限定、「~だけ」は中立的な限定という違いがあります。
⑰「〜きり」と「〜だけ」
<共通点>
「〜きり」と「〜だけ」はいずれも、数や範囲を限定する意味を持ちますが、その後の継続や唯一性に違いがあります。
<違い>
■「〜きり」は、その後の変化がなく、そのままの状態が続いている場合に強調して使います。また、孤立感や寂しさのニュアンスを含むことがあります。
例文:一人きりで食事をしました。
■「〜だけ」は、数や範囲を単に限定したいときに使います。
例文:一回だけ参加しました。
ポイント:「〜きり」は継続感や孤独感を、「〜だけ」は範囲の限定を表します。
⑱「〜ばかり」と「〜だけ」
<共通点>
「〜ばかり」と「〜だけ」は二つとも、数や範囲を制限を表す語ですが、「ばかり」には偏りや回数の多さが含まれます。
<違い>
■「〜ばかり」は、同じことが何度も起こったり、量や頻度が多かったりすることを強く表すときに使います。
例文:スマホばかり見ています。
■「〜だけ」は、数量や範囲を単純に限定したいときに使います。
例文:今日は国語の勉強だけします。
ポイント:「~ばかり」は偏りや反復・量を示し、「~だけ」は範囲や数の限定のみを示します。
⑲「〜といえば」と「〜といったら」
<共通点>
「〜といえば」と「〜といったら」は両方とも、話題を出したり強調したりするときに使います。
<違い>
■「〜といえば」は、話題の導入や代表例をあげるときに使います。
例文:京都といえば、古い寺院や神社が有名です。
■「〜といったら」は、程度が甚だしいことを強調する表現で、驚きや感嘆を込めて使われます。
例文:彼の歌の上手さといったら、プロ級です。
ポイント:「~といえば」は話題の導入、「~といったら」は強い驚きや感情の表現です。
⑳「〜ものの」と「〜とはいえ」
<共通点>
「〜ものの」と「〜とはいえ」はどちらも、逆接や譲歩を表す接続詞です。
<違い>
■「〜ものの」は、事実として認めながらも、期待通りにならない場合などに使います。
例文:試験に合格したものの、実際の業務は難しかった。
■「〜とはいえ」は、事実や一般論を認めて、さらに例外や補足説明を加えるときに使います。
例文:秋とはいえ、まだ暑いです。
ポイント:「〜ものの」はギャップや不満を、「〜とはいえ」は譲歩や追加説明の場面で使います。
おわりに
以上のように、日本語にはさまざまな表現方法があります。使い方によっては、意図しないニュアンスの違いを引き起こすことになりかねません。
特に多くの人の目に触れる文書やビジネスシーンでは、文章の細かな言い回しにまで配慮する姿勢が大切です。表現のわずかな違いにも気を配ることで、より伝わりやすい文章に仕上げることができます。

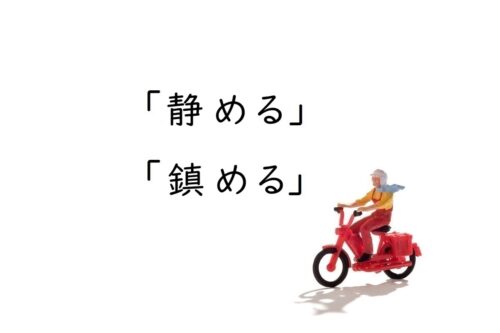






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Indentation-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)
