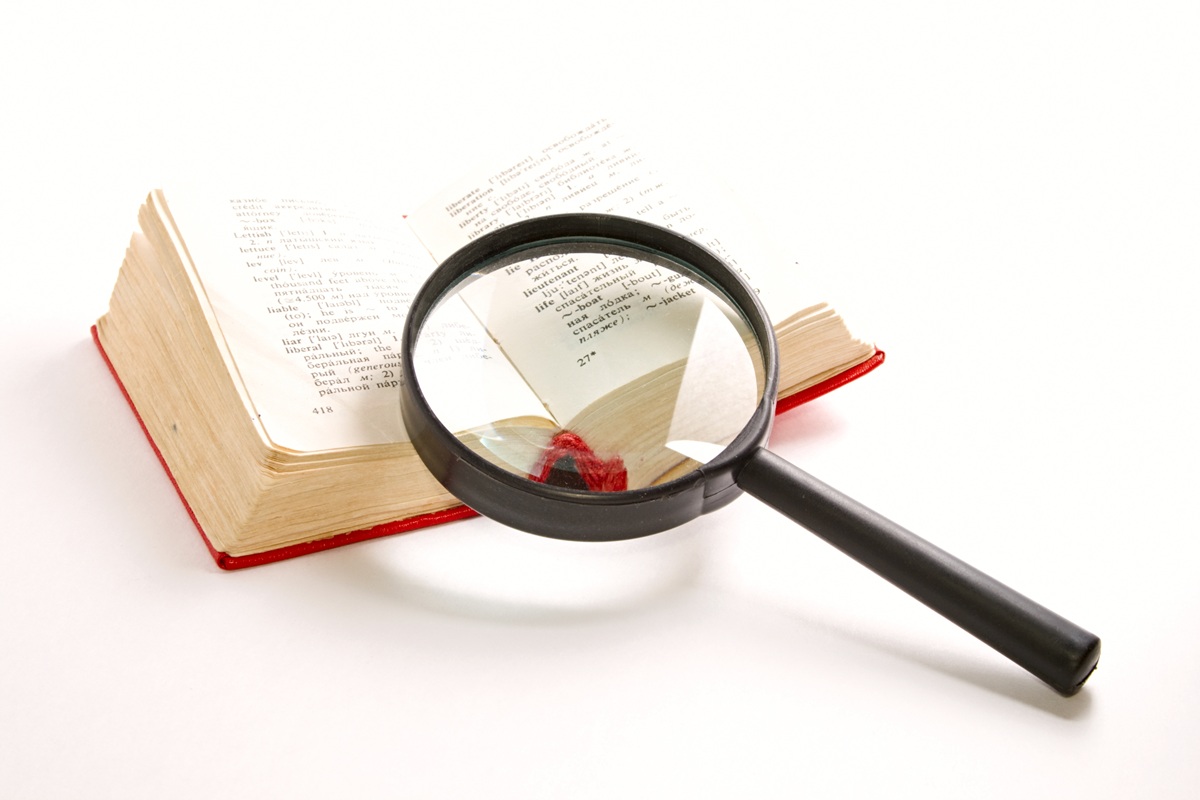
歴史のファクトチェックに潜む3つの罠:校正者でも迷うポイント
校正の事実確認(ファクトチェック)の中には、歴史的事項の確認も含まれます。単純な人名のチェックなどであれば比較的容易ですが、歴史的事項に特有の、一筋縄ではいかないものもあります。この記事では、そうした事項をチェックする際のポイントを解説します。
[記事作成にあたっては、以下の書籍・辞書・サイトを参考にしています]
・『東京大学本部コミュニケーション戦略課』
・『レファレンス協同データベース』
・『コトバンク』デジタル大辞泉(小学館)
1. 固有名詞のファクトチェック
■ 固有名詞
次の文章は歴史的に適切ではありませんが、どこが問題かかるでしょうかわかるでしょうか。
明治20年、東京帝国大学に入学するため、東京市に居を移した。大学ではソ連出身の教授のもとでロシア文学を学んだ。
この文中に、歴史的に適切でない箇所は3つあります。
① 明治20年時点では「東京帝国大学」ではなく「帝国大学」
明治30年、「京都帝国大学」の創設に伴って「帝国大学」から「東京帝国大学」と改称されています。
② 明治20年時点では「東京市」は存在しない
「東京市」は明治22年、「東京府」の管轄地内に設置されました。
③「ソ連」の成立は大正時代
ソ連が成立したのは1922(大正11)年なので、明治20年ごろに「ソ連出身の教授」はいないと考えられます。
国名や市区町村名、組織名などは、時代とともにさまざまな変遷を経ているものが多くあります。文脈から年月や時代が読み取れる場合は、単に名称をチェックするだけでなく、本当にその時期にその名称だったのか、そもそもその時期に存在していたのかなどの確認も必要です。
2. 新暦・旧暦のファクトチェック
■ 新暦・旧暦
幕末、ペリーが黒船を率いて浦賀に入港したのは嘉永6年6月3日のことです。嘉永6年は西暦1853年に当たります。つまりペリー来航は1853年6月3日……となれば分かりやすくていいのですが、そう簡単にはいきません。
1872年までの日本では「太陰太陽暦」が使われていました。いわゆる「旧暦」です。この暦では1年が354日とされ、1年を365日とする太陽暦(1873年から現在まで使われている暦。いわゆる「新暦」)とはズレが生じます。たとえば享保8年は、1723年2月5日~1724年1月25日に当たります。ちなみに、ペリー来航の嘉永6年6月3日は、西暦に換算すると1853年7月8日となります。
歴史的な内容の中で日付が出てきた際は、新暦なのか旧暦なのかを意識しながらチェックしましょう。新暦と旧暦の対応を調べる際に役立つ資料を紹介しておきます。
国立天文台ホームページの「日本の暦日データベース」(https://eco.mtk.nao.ac.jp/cgi-bin/koyomi/caldb.cgi)では、西暦から和暦・和暦から西暦のいずれも変換することができます。ある日付の対応をピンポイントで知りたいときに便利です。
1701(元禄14)~1911(明治44)年については、外務省のホームページに詳細な対照表が掲載されています(https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/kindai.html)。このほか、国立国会図書館ホームページでもさまざまな資料があげられています(https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/stm/post_400108)。
3. 数え年のファクトチェック
■ 数え年
現代の日本で年齢を数えるときは、生まれたときを0歳とし、誕生日を迎えるごとに年齢が1歳増える「満年齢」が使われています。しかし満年齢が一般的に使われるようになったのは、1950年施行の「年齢のとなえ方に関する法律」によって満年齢の使用が推奨されてからであり、その歴史は意外と浅いです。
この法律以前は、生まれたときを1歳とし、新年を迎えるごとに年齢が1歳増える「数え年」が使われていました。
歴史上の人物の場合、年齢表記は数え年が使われることが多いようです。同一人物について、また同時代の人物について、数え年と満年齢が混在していないか留意しましょう。
特に、数え年から満年齢に切り替わった1950年より前に生まれ、それ以降も存命だった人物については、どちらの数え方を採るか揺れやすいので注意が必要です。
おわりに
以上、歴史的事項の事実確認についての注意点を解説しました。
歴史的な内容をチェックする際は、現代の一般的な文章を校正するときとは異なる前提知識が必要とされます。この記事で解説したポイントを踏まえて、注意深く確認しましょう。

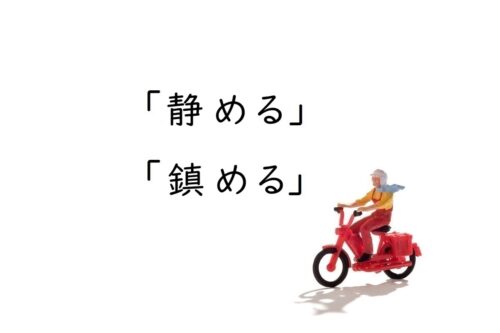






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Indentation-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)
