
漫才師であり日本語学の専門家の目に映る「校正・校閲」の世界とは?
今回の記事は、書籍『校正・校閲11の現場 こんなふうに読んでいる』の書評です。執筆者は、お笑いコンビ「米粒写経」として活躍される漫才師でありながら、東北芸術工科大学で講師も務めるサンキュータツオさんです。日本語やお笑いを専門とする、まさに言葉のプロフェッショナルが校正・校閲に関する書籍を書評するという他にはない深い視点が体験できる記事になっています。
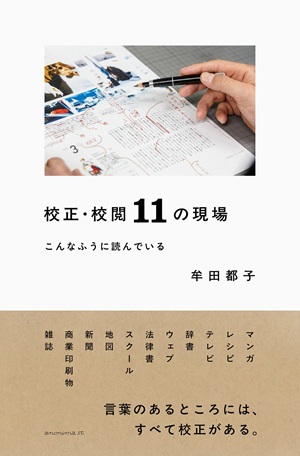
『校正・校閲11の現場 こんなふうに読んでいる』
(牟田都子 (著)、アノニマ・スタジオ)
縁の下の力持ちの仕事に敬意
言葉あるところに校正者あり。出版の世界では「最後の砦」「ゴールキーパー」 とたとえられているが、その存在は誤字などが見つかったとき意識されるという宿命を背負っている。陰の存在でありながら責任重大な仕事である―
というところまではご存じかもしれないが、それぞれの校正者に得意ジャンルや専門性があり、使う脳みそも道具も、求められる能力にも違いがあるというところまではなかなか知ることができない。なにより校正者同士が交流する場というものがあまりない。『文にあたる』で校正者としての思索をまとめた著者が、本書では異なる11ジャンルの校正者たちに会いに行く。拾い上げたエピソードの数々に驚くことが多い、貴重な資料だ。レシピには材料の並び順が存在することも知らなかった。スポーツマンガでは「背番号は変わると思え」「兄弟は入れ替わりがち」なんて法則も面白い。テレビ校正和氣亜希子さんはいう。「スーパーで食材を大量に買って料理をするような企画では、買った食材と量・値段をエクセルに書き出して、買ったものが確かに料理に使われたか、量に過不足がないか、セルに色を塗りながら確認します。(中略)『302品買いました』という映像の品を数えてみたら280品しかないなど、30分ほどの映像で、指摘は100を優に超えます」
めまいがするような信じがたい作業だ。テレビやウェブでは求められるスピードも書籍とは違う。用字用語の統一だけでなく、内容の正誤、踏み込みすぎた発言に対する懸念など、作業は編集者の領域にも及ぶが、著者や編集者との距離感も大事にしなければならない。
地図の校正では地名の表記不統一や名称変更のチェックなど、実例を見るだけで驚愕するだろう。縁の下の力持ちたちの仕事に自然と敬意がわいてくる。紙は減るかもしれないが、言葉は減らない。私たちが活字を読める幸福は、彼らの慎ましい矜持に支えられている。
サンキュータツオ
(漫才師、東北芸術工科大学講師)
2025年2月1日朝日新聞
承諾番号:25-2218
朝日新聞社に無断で転載することを禁じる。

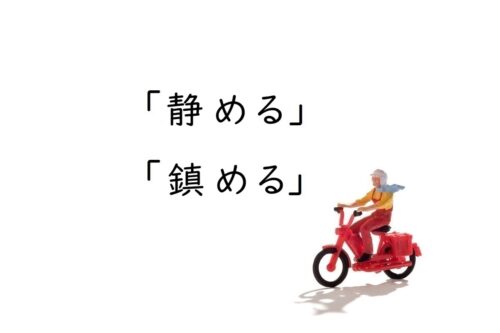






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Indentation-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)
