![1行あける(1行アキ)の使い方[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/open-one-line-in-proofreading-mark.jpg)
目 次
1行あける(1行アキ)の校正記号の使い方
※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。
1. 1行あける(1行アキ)の校正記号
▼ 1行あけたい場合
「1行アキ」もしくは「1行アケル」の指示を使います。
※ここでは、「1行アキ」を使用していますが「1行アケル」も同様の使い方です。
<赤字の入れ方>
● 横書き
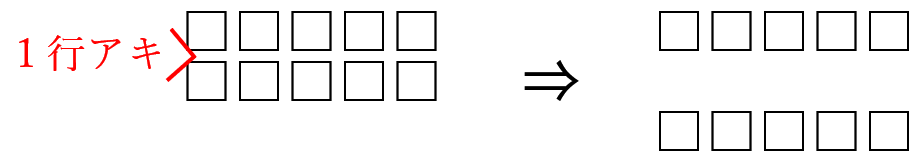
● 縦書き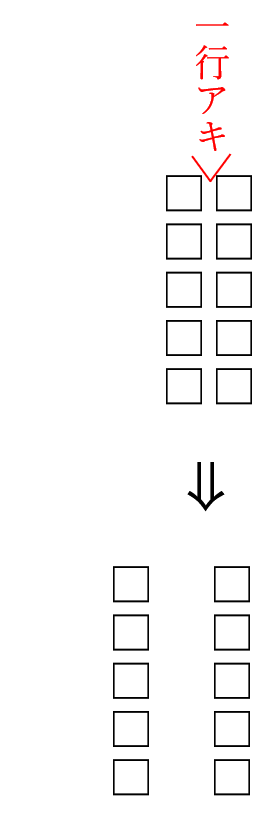
2. アキを調整して1行あきにしたい
▼ 既にアキがあるものを、1行あきにしたい場合
「1行アキニ」の指示を使います。
<赤字の入れ方>
● 横書き
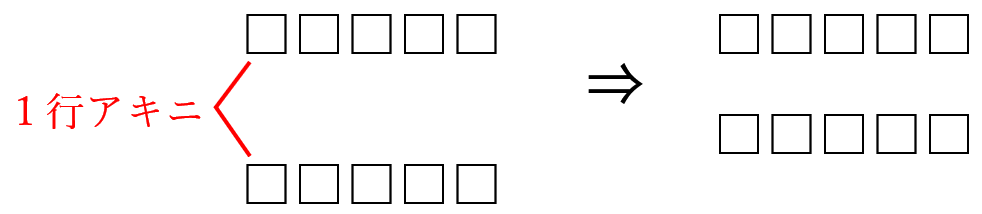
● 縦書き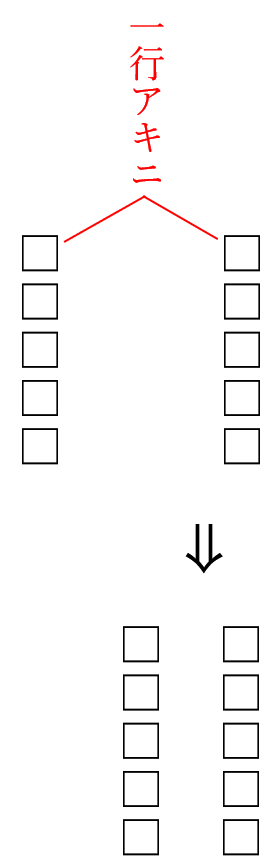
→「1行アキニ」の指示だけで、何行分のアキがあっても、1行分の空きにすることができます。
3. 1行あける(1行アキ)<応用編1>
▼ 1行あけるときのポイント
行をあける場合、横組みなら基本は下へ広がります。
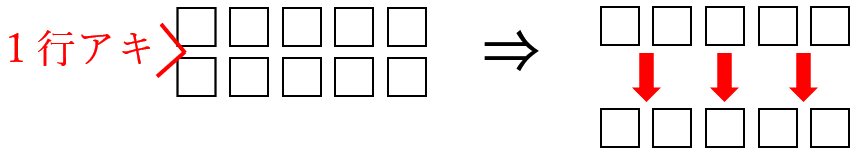
ですが、次のように上に広げたい場合もあると思います。
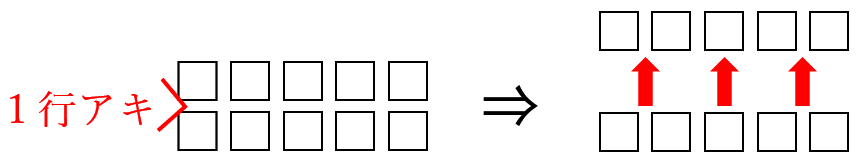
こうしたい場合には、何らかの補足指示を入れる必要があります。
<赤字の入れ方>
【例1】
・上に移動させる指示を付け足す
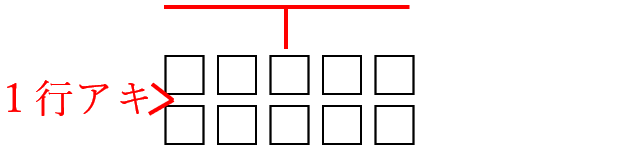
【例2】
・文字で補足する(補足の指示なので鉛筆書きにしています)

4. 1行あける(1行アキ)<応用編2>
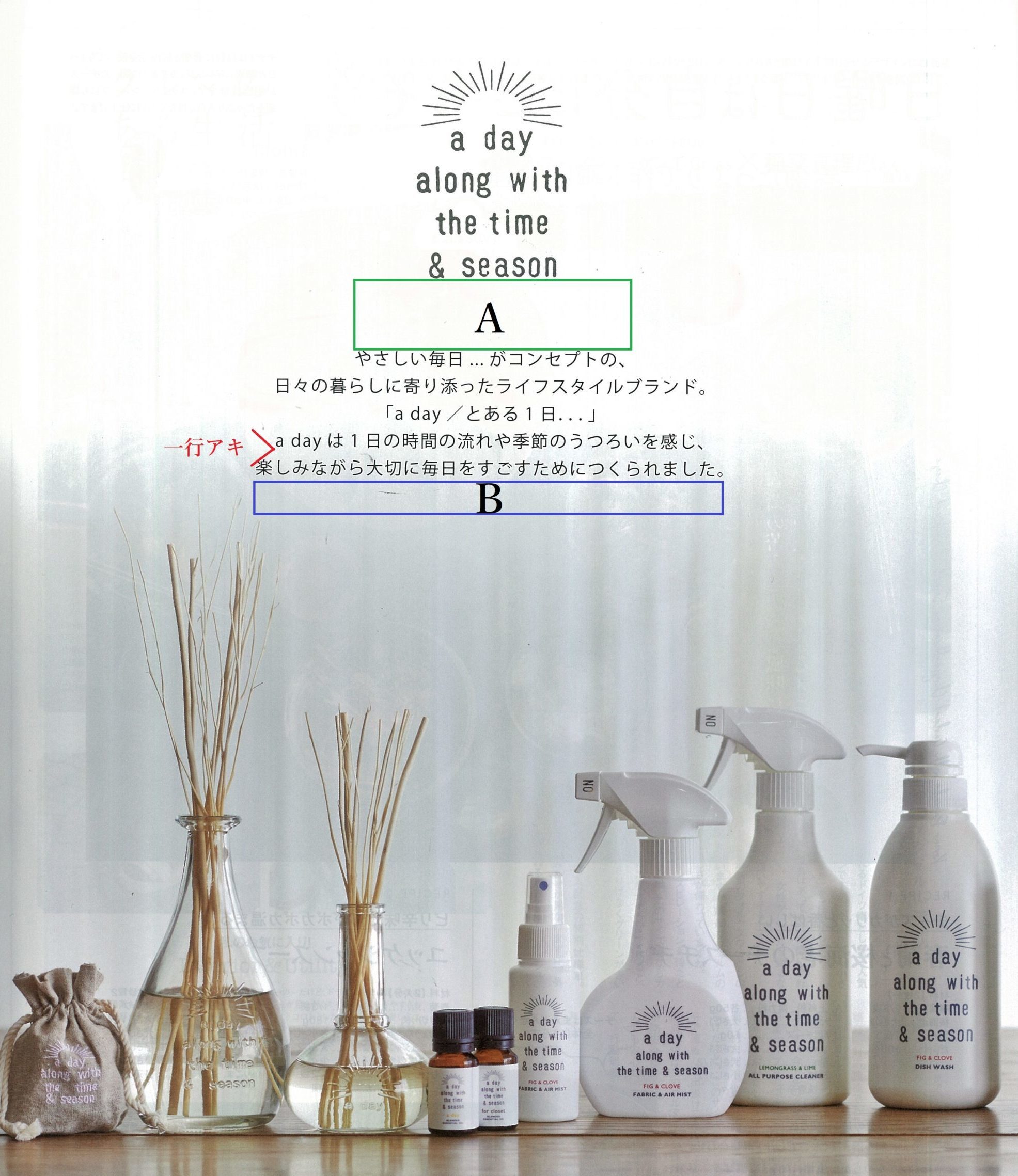 【出典:『InRed』2020年3月号(宝島社)P.132より】
【出典:『InRed』2020年3月号(宝島社)P.132より】
コピー部分に「一行アキ」の指示があります。ここでは「一行アキ」だけだと言葉足らずになってしまう可能性があります。
一行分のアキが入ったことで、
・Aのアキで調整するのか?
・Bのアキで調整するのか?
といったことも考える必要があります。
「Aのアキ」をツメて調整する場合、すぐ上にあるロゴに注意しなければいけません。
企業ロゴには、ほぼすべてにレギュレーション(規定/ルール/決まり)が存在します。レギュレーションには、ロゴ周りの余白・配置位置・大きさ・色・フォントなどロゴの使用方法が詳細に記載されています。大抵ロゴ周りのスペースは余白を確保する必要があるため、スペースがあっても使えないことがほとんどです。
ロゴ周りに一定のアキを確保する規定があるのなら「Aのアキ」で調整することはできません。「Bのアキ」で調整するしかありません。ですが「Bのアキ」で調整すると、Bの左下部分の画像と下げた文字が重なる恐れがあります。
普通の文章なら「一行アキ」の指示を入れるだけで大丈夫ですが、このようなレイアウトの場合は、「一行アキ」の指示を入れるときに、もう一歩踏み込んで考えなくてはいけません。
デザインを変更する(コピーの級数を変える、画像を小さくするなど)こともあるので、そこは担当者と相談しましょう。

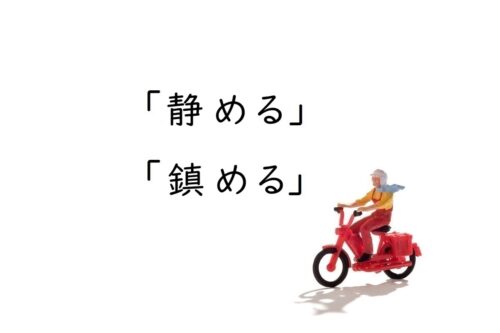






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)
![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

