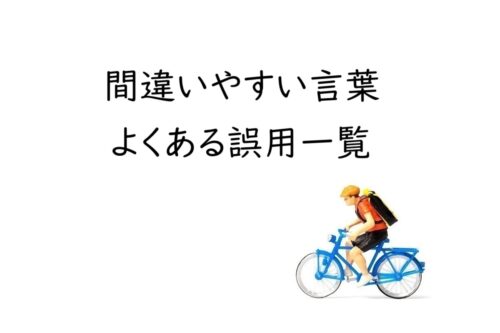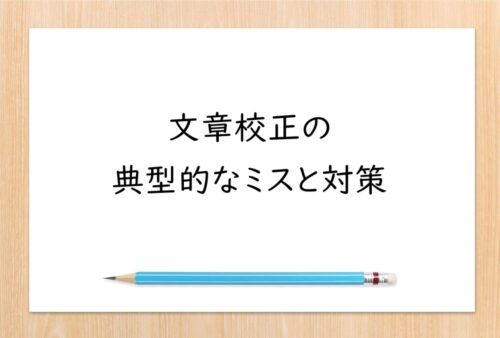文章校正のコツ:あえて疑問を出さない校正者の重要なスキル
校正ゲラにびっしり疑問出しが入っていると素晴らしい校正者のように見えるかもしれませんが、実は疑問の量と校正者の技量とは必ずしも比例しません。「あえて疑問を出さない」ことも、校正者の重要なスキルです。
この記事では、どういった場合に「あえて疑問を出さない」ことが必要になるのか、またなぜ大量の疑問を出すのがいい校正とは限らないのかを解説しています。
1. 疑問を出さないほうがいいケース
疑問出しを控えたほうがいいケースは、大きく2つあります。1つは「著者の意図が感じられる場合」、もう1つは「再校以降である場合」です。それぞれについて具体例をあげながら説明したいと思います。
▼ 著者の意図が感じられる場合
当然のことではありますが、校正者が読む文章にはそれを書いた著者がいます。校正する際には、自分の感覚だけに基づいて疑問を出すのではなく、ゲラの背景にある著者の意図を常に意識することが重要になってきます。
・表記の混在
一見表記ゆれのように思える場合でも、意図的に使い分けされている言葉もあります。たとえば、小説で登場人物によって一人称が「僕/ぼく/ボク」などと書き分けられているといったものです。
正式名称と略称が使い分けられているパターンもあります。たとえば「厚生労働省」と「厚労省」がばらついているように見えるものの、詳しく見てみると各章の初出では正式名称の「厚生労働省」、2回目以降は略称の「厚労省」となっているようなケースです。
表記のばらつきが見られたときには機械的に統一する疑問出しをするのではなく、まずは法則性が見いだせないか考えるようにしましょう。
・本来の用法ではないが許容とされる表現
日本語の言い回しの中には、本来は適切ではないものの慣用的に広く使われ、許容とされている表現があります。たとえば「かねてから」という表現がそうです。「かねて」自体に「以前から」という意味があるため、本来は「かねてから」とすると重複表現となります。
しかし、『新明解国語辞典(三省堂)』には「かねてから」が見出し語としてとりあげられており、『明鏡国語辞典(大修館書店)』の「かねて」の項には、「『かねてより』『かねてから』は本来は重言だが、古くから使う」との記述があるなど、慣用的に使われている表現です。
ゲラ内で「かねて」と「かねてから」が混在しているなら、本来の用法である「かねて」とする疑問を出す手もありますが、「かねてから」のみが複数回出てくるようであれば意図的に使われているかもしれません。疑問を出すとしても、逐一「かねて」とするのではなく、初出にのみ「本来は重複表現とされますがママとしますか?」といった注意喚起をするにとどめるなどがいいでしょう。
・専門用語/業界特有の言い回しなど
日常的には耳慣れない表現であっても、特定の分野や業界では広く使われていることがあります。たとえば「人日(にんにち)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
作業量を表す言葉で、3人で2日かかる仕事は6人日というように使われます。日常生活ではあまり耳にすることはありませんが、IT業界では人件費の見積もりなどによく使われます。このように、自分の感覚では違和感があったり、国語辞典類で確認できなかったりしても、業界用語のように通用している表現は数多くあります。
こうした表現が出てきた際は、インターネット検索を活用しましょう。問題となる表現と、ゲラ内でそれに関連している語とを合わせて検索し、同様の表現が使われているページが複数ヒットするようであれば、その分野では使われている言い回しなのだと判断できます。たとえば上述の「人日」が「15人日で見積もりを出した」という形で出てきていたら、「人日 見積もり」で検索してみます。そうすると、IT業界において見積もりをするための作業量の単位として「人日」が使われているページが複数ヒットするため、その業界では通用している表現であることがわかります。
特に専門書であれば、予備知識のない校正者にはわかりにくく思われても、その分野に通じている読者にはスムーズに理解できる場合があります。逐一書き換えるなどするとかえって煩雑になる恐れもあるので、疑問は控えめにしたほうがよいでしょう。
ただし一般向けの書籍などの場合は、あまりに専門的・特殊な表現については、読者の理解のために言い換えや補足説明をしたほうがよいことがあります。疑問を出すかどうか、またどのような疑問を出すかは、読者層などを考慮して総合的な判断が必要です。
▼ 再校以降である場合
初校ではもちろんゲラ全体をまんべんなくチェックしますが、再校では初校で加筆や修正された部分を重点的に校正します。三校以降も同様に、前の工程で修正が入った部分を中心に確認します。
そのため校正の疑問出しは基本的に、初校より再校のほうが少なく、再校より三校のほうが少なくなるというように、工程が進むほど減っていくものです。
初校と再校以降では、疑問の質も異なります。初校では誤字脱字のほかに文法的な誤り、全体の整合性にかかわるような疑問出しなどを入れますが、再校以降では誤字脱字のような致命的な部分の指摘が中心になります。
たとえば再校を担当していて日本語的な表現が気になったとしても、初校担当者は疑問出しをしていないことがあります。つまり、誤りとまでは言えず、好みの問題の範囲に入るケースです。このような部分に関しては、再校で改めて疑問出しするほどではないと判断し、あえて疑問を出しません。
加えて、案件の進行の観点から見ると、工程が進むほど刊行までの日程が迫ってきます。出版間際になって大幅な修正が入るのは避けたいので、明らかな誤りでなければ疑問を出しても却下されやすいです。
こうしたことから、初校であれば出したであろう疑問出しでも、再校以降のタイミングではあえて出さないという判断が必要になってきます。自分が担当している工程が全体の進行の中でどの段階にあるのか、意識することが重要です。
2. あえて疑問を出さないほうがいい理由
ここまで、あえて疑問を出さないほうがいいケースについて説明してきました。それでは、なぜこうした場合には疑問出しを控えたほうがいいのでしょうか。1つは、疑問出しの量が多くなることによって重要な指摘が見逃される場合があるからです。もう1つは著者の心証が悪くなる恐れがあるためです。
▼ 重要な疑問出しが見逃されることがある
上にあげたような例についてすべて疑問出しをすると、ゲラ全体での疑問の量が多くなります。ゲラ上で疑問出しの文字が混み合っていると、誤字脱字などの重要な指摘が埋もれてしまいやすくなるのです。疑問出しの量が多いときは特に、必ず修正すべき(確認すべき)箇所への指摘が見落とされないように、重要度が比較的低い疑問出しは控えたほうがよいです。
▼ 著者の心証が悪くなる恐れがある
自分が書いた文章に対して疑問出しを入れられるのは、一般的にはあまり気分が良くないものです。その疑問が、意図的に使い分けている表記に対するものなどであればなおさらです。そうした部分で著者の心証を損ねると、必ず検討してほしい部分の疑問出しまで確認してもらえなくなる恐れがあります。著者の意図を尊重しながら、本当に再確認が必要な部分については漏れなく対処してもらえるように努めましょう。
おわりに
校正をしていると気になる箇所が多々出てきますが、上で述べたように、それらすべてに対して片っ端からが疑問を出すのがいい校正とは限りません。本当に疑問出しが必要な部分なのか、常に考えながら校正するようにしましょう。

![素読みをするときの基本ポイント[文章校正の基礎]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/read-a-text-500x333.jpg)
![校閲者の仕事への考え方と取り組み方[例文で学ぶ文章校正に必要な確認ポイントと校閲の視点]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Tips-and-Iideas-for-proofreading-500x334.jpg)

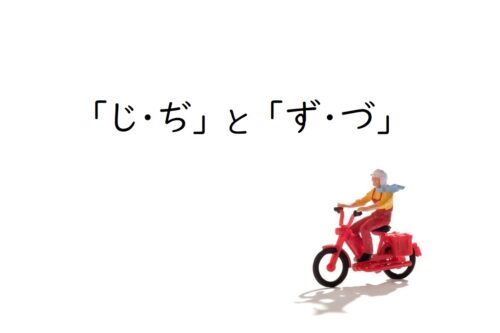
![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
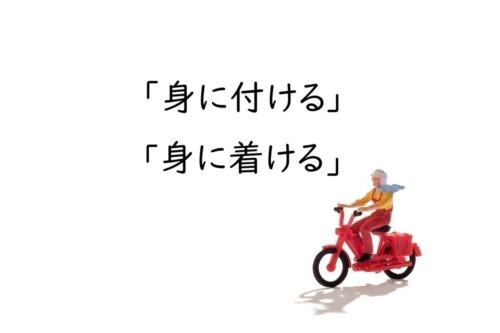
![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)
![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)
![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)