![社会人になって知る日本語の大切さ[超基本:ビジネスシーンで躓かない言葉の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/08/Japanese-words-usage.jpg)
目 次
社会人になって知る日本語の大切さ[超基本:ビジネスシーンで躓かない言葉の使い方]
日本語は、話し相手や状況に応じてさまざまな表現を使い分けることができる言語です。その一方で、「どの表現が最も適切なのか」「本当に正しく使い分けられているか」など迷うことも少なくありません。
特に学校教育だけでは、言葉の微妙なニュアンスや使い分けについてまで十分に学ぶ機会がありません。そのため社会人になってから「正しい言葉を使えているか」「この敬語は失礼ではないか」などの問題に直面することも多いです。
この記事では、日本語表現の使い分けについて、ビジネスや日常生活に即した基本的な誤りやすい例を紹介します。日々のメールや会話、文章の作成などにお役立てください。
▼ 文章作成・校正の際に社内に辞典類がない、表記ルールがないという場合は、以下の書籍が役立ちます。
■『記者ハンドブック 第14版:新聞用字用語集』(一般社団法人共同通信社)
→ 文章作成者向け。様々な表現が掲載。
■『日本語の正しい表記と用語の辞典 第三版』(講談社)
■『新しい国語表記ハンドブック 第九版』(三省堂)
→ 日本語の使い方を網羅的に記載。文章の作成から表記の確認など代表的なものを掲載。
書籍選びの際には商品レビューの評価が高くても、内容が自分の業務に合わないことや、相性(見やすさ・調べやすさ)があるので、実際に書店で手に取って中身を確認してから購入することをおすすめします。
これらの三冊をいずれも所有していますが、頻繁に活用しているものは、二色刷りで見やすい『新しい国語表記ハンドブック』です。辞典や参考書を購入したものの、それで満足してしまい、実際にはほとんど使っていないという方もいると思います。「相性」は、辞典を継続的に利用するうえで重要なポイントです。
▼ PCで日本語を調べたいという方は次の記事も参考にしてみてください。
1. 漢字とひらがなの使い分け
日本語には、「従って」と「したがって」、「但し」と「ただし」のように、同じ読みでも表記によって印象が異なる語が多くあります。文法的にはどちらも正しいですが、同じ文書の中で表記が混在すると、違和感や読みづらさが出てきます。
漢字とひらがなをどう使い分けるかは、単なる見た目の問題だけでなく、読む人にどのような印象を与えたいか、どうすれば伝わりやすいかといった点にも関わります。文章の使用場面や目的に合った表記を選び、統一することで、文章をより明瞭に読みやすくすることができます。
たとえば、公的な文書やビジネスの報告書では、漢字の割合を高めることで厳格さが増し、文全体が引き締まった格式ある印象を与えることができます。一方、社内メールや一般的なWebの記事などでは、文書内のひらがなの割合を高めることで、文をやわらかくし親しみやすさを高めることができます。
■ 硬さを求める文章
『この調査結果に従って、今後の方針を決定いたします。但し、状況の変化によっては再検討いたします。』
⇒ 漢字を使うことで、整然とした厳格な印象を与えます。
■ やわらかさを求める文章
『この調査結果にしたがって、今後の方針を決定します。ただし、状況の変化によっては再検討します。』
⇒ ひらがなを使うことで、文体がやわらかく親しみやすい印象になります。
<よく見られる「漢字」と「ひらがな」の使い分け例>
一般的に形式名詞や補助動詞は、ひらがなで書くようにするルールが多く見られますが、漢字とひらがなのどちらの使用が正しいかというよりも、その文書の使用場面や読み手にとってふさわしい表記を心がけることが大切になってきます。
①「こと/事」「とき/時」
抽象的・概念的な内容なら「こと」「とき」とひらがなで、具体的な事象や数字と結びつく場合は漢字で書くという使い分けもできます。
【例】抽象的:「何かを学ぶことは大切です」/具体的:「事故が発生した時に」
②「出来る/できる」
出版物や公的文書では「できる」と表記するのが主流です。
③「為/ため」
法令や契約書、歴史的文書では「為」と漢字を使う例も見られますが、通常の文章では「ため」とひらがなで書くのが一般的です。
④「勿論/もちろん」
漢字の「勿論」はやや堅く、あらたまった雰囲気になり、ひらがなの「もちろん」は軽やかでやわらかい印象になります。
このほかにも、「及び/および」や「又は/または」、「尚/なお」など、場面によって漢字とひらがな両方が使い分けられるものは色々とあります。
漢字表記は格式や公的な雰囲気が生まれるため、契約書や報告書といった公式文書に向いています。一方、ひらがな表記は文章をやわらかく、親しみやすく見せたいときに有効です。また、「為」や「勿論」などは常用漢字でないため漢字の使用を控えるといった傾向もあります。
表記に関して絶対の正解はありませんが、一つの文書内で同一語の表記が「漢字」と「ひらがな」で揺れないようにするのが一般的です。そのため表記ルールを作成している企業も多いです。
2. ビジネスシーンで敬語の適切な使い方
ビジネスシーンにおいて、メールや文書の作成時に敬語を正しく使い分けられるかは重要です。敬語の使い方次第で、相手に与える印象や、その後のやりとりの円滑さが大きく左右されます。また、敬語は単なるマナーとしてだけでなく、社会人としての信頼性を高めるためにも欠かせない要素です。
同じような意味合いに見える敬語でも、場面によって選ぶべき表現は異なります。敬語の適切な選び方は、相手への敬意や自分の丁寧な姿勢を伝えるだけでなく、信頼を築くうえでも重要です。
①「申し訳ありません」と「申し訳ございません」
「申し訳ありません」は、日常的なビジネスシーンや比較的軽度な謝罪でよく使われる表現です。ミスや遅延が生じた場合に「この度はご連絡が遅れ、申し訳ありません」といった形で用います。社内や親しい相手に対しても使えます。
「申し訳ございません」は、より改まった謝罪表現で、お客様や取引先、上司、公式な場面で深く謝罪を伝えたいときに使われます。「この度は多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と表現することで、より強い誠意を示せます。
②「拝見いたしました」と「拝読いたしました」
「拝見」は「見る」「確認する」の謙譲語で、写真、資料、商品、Webページなど視覚的に目を通した場合に使います。
【例】「お送りいただいた契約書の原本を拝見いたしました」
「拝読」は「読む」の謙譲語で、メールや書簡、書籍といった文章を読んだ際に使います。
【例】「ご送付いただいたレポートを拝読いたしました」
③「ご確認ください」と「ご査収ください」
「ご確認ください」は、主にメールや連絡文で相手に情報や内容を確認してほしいときに使います。
【例】「添付資料の内容をご確認ください」
「ご査収ください」は、請求書や領収書、発送した商品など、実際にものが届いた際に受け取りを確認してもらう場合に使います。
【例】「書類を郵送いたしましたので、ご査収ください」
④「ご教示ください」と「ご教授ください」
「ご教示ください」は、方法や手順など具体的な事項を教えてほしいときに使用します。
【例】「操作方法をご教示ください」「手順をご教示願います」
「ご教授ください」は、より専門的な知識や技術について、時間をかけて指導してもらう場合に使われます。
【例】「◯◯についてご教授いただけますと幸いです」
⑤「承知しました」と「かしこまりました」
返答の際も、相手や状況に応じて敬語を使い分けることが必要です。
「承知しました」は同僚や目下の方、または親しい間柄で幅広く使われます。
「かしこまりました」は、目上の方や取引先、お客様など、より丁寧で改まった印象を与えたいときに適切です。
⑥「〜させていただきます」
「させていただきます」は、もともと相手の許可や配慮が前提となる丁寧な表現です。しかし、近年では過度に使われることが多く、くどい印象を与えることも多いです。
たとえば「明日、お電話させていただきます」なら、「明日、お電話いたします」としたほうがすっきりします。
また、相手の都合や予定を考慮する場合は「明日、お電話してもよろしいでしょうか」と依頼の形にすることも可能です。他にも、「ご質問があれば、お答えさせていただきます」を「ご質問があれば、お答えいたします」といったように簡潔に言い換えることもできます。
⑦「至急」と「早急」
「至急」は、「ただちに対応してほしい」という強い要請がある場合に使います。「至急ご連絡ください」など、すぐに行動を促したいときに適しています。
「早急」は、「できるだけ早く対応をお願いしたい」といった、至急よりもやや緊急度の低い場合に使用します。「早急にご対応をお願いいたします」というように使います。
⑧「ご高覧ください」
「ご高覧ください」は、資料や書類などに目を通してもらいたい際に使います。「添付資料をご高覧くださいますよう、お願い申し上げます」といった形が一般的です。
⑨「拝受しました」
「拝受しました」は、何かを受け取ったことを丁寧に伝える表現です。書類や贈り物、資料などを確かに受領したことを知らせる際に用いられます。たとえば「ご送付いただいた資料、確かに拝受いたしました」などです。
⑩「伺う」「参る」「お邪魔する」
いずれも自分が相手先に行く際に使いますが、ビジネスでは「伺う」が最も自然な表現で、「参る」はやや硬く、「お邪魔する」はカジュアルな印象です。
⑪「いただく」と「くださる」
「いただく」は自分がもらうときの謙譲語、「くださる」は相手がくれる場合の尊敬語です。
⑫「いただきます」と「頂戴します」
通常は「いただきます」で十分ですが、より改まった場面では「頂戴します」を用います。
敬語の使い分けのポイントは、相手との関係や自分の立場、使用場面(社内・社外・公的・私的など)を意識して適切な表現を選ぶようにします。必要以上に丁寧にしすぎないよう、自然で過不足のない敬語を心がけるのがポイントです。
3. 言葉の微妙なニュアンスによる使い分け
日本語には、意味が似ていても使う場面やニュアンスが異なる語が数多くあります。これらの言葉を正しく使い分けることで、文章や会話がより的確で伝わりやすくなります。一見同じ意味のように見える表現でも、使い方によって相手に伝わる印象や論理の明確さが大きく変化します。ひとつの語の誤用によって、読み手に誤解が生じたり、文書全体の評価が下がることも少なくありません。
①「知る」と「わかる」
「知る」は、情報や事実の存在そのものを認識している状態を指します。「名前を聞いたことがある」など、とりあえず情報として知っている場合に使います。
【例】「彼の名前は知っています」「その現象について知っている」
「わかる」は、単に知っているだけでなく、その中身や意味、本質をきちんと理解している場合に使います。
【例】「彼がなぜそう言ったのか、理由がわかった」「この数式の意味がわかる」
<比較例>
「彼の名前は知っているが、どんな人かはわからない」
「校正という仕事は知っているが、どんな内容なのかまではわからない」
②「理解している」と「認識している」
「理解している」は、内容や仕組みを理屈も含めて把握し、説明や応用ができる水準で知っているときに使います。
【例】「この理論は十分に理解しています」「仕組みを理解してから作業に入ります」
「認識している」は、事実や状況について気づいている、把握している、という意味合いです。深く掘り下げていなくても、「こうした課題が存在する」とわかっているときに使います。
【例】「新システム導入の課題は認識しています」「納期が大切であることは認識しています」
<比較例>
「この技術の原理については理解していますが、現場での問題点はまだ十分認識していません」
③「示す」と「表す」
報告書や論文では、データや現象、解釈を正確に表現する必要があります。そのため、動詞にも配慮しなければいけません。
「示す」は、図や数値など客観的事実を提示するときに用います。
【例】「図1は実験結果を示している」
「表す」は、言葉や記号、式などで意味や内容を示す場合に使用します。
【例】「式1は変数XとYの関係を表す」
④「推測」と「推定」
両者は「何か確実ではないことを考える」という点で似ていますが、根拠に違いがあります。
「推測」は、主観的な判断や予想で使い、はっきりした根拠がない場合に「たぶん~だろう」と考えるときの表現です。
【例】「彼の表情から、忙しいのだと推測する」「天気予報から午後は雨と推測する」
「推定」は、具体的な数値やデータなど客観的な根拠から冷静に「~と判断する」場面で使います。
【例】「統計データから人口は50万人と推定される」「売上の10%減少が見込まれると推定される」
⑤「保証」「保障」「補償」
似た漢字ですが、それぞれ異なる意味を持ちます。
「保証」は、品質や性能などを約束する際に使います。
【例】「商品の品質を1年間保証します」
「保障」は、権利や安全、状態などの維持・確保を意味します。
【例】「表現の自由を保障する」
「補償」は、被害や損害が生じた場合に、その埋め合わせを行うことです。
【例】「事故による損害を補償する」
4. 誤用しやすい表現
日本語は、時代や世代による意味の変化や誤用が一般化しやすく、誤った表現が浸透していることもあります。
公的文書やビジネス文書など、正確さが求められる場面では、言葉の使い方一つで説得力が大きく左右されます。普段の会話や慣習的に、誤用が許容とされることもありますが、公式の場面では相応しくありません。それぞれの言葉の本来の意味と正しい用法を理解しておくことが大切です。
以下はほんの一例ですが、前述した三冊の書籍には、このような事例がたくさん取りあげられています。
<よくある誤用例と本来の意味>
①「的を得る」→「的を射る」
(誤)「その発言は的を得ている」
(正)「その発言は的を射ている」
【本来の意味】:「弓矢で的を射抜く」ことから、物事の核心をついているという意味。ただし、「得る」も問題ないとされることも多いです。
②「煮詰まる」
(誤)「議論が煮詰まってしまった(行き詰まった)」
(正)「議論が煮詰まり、結論が見えてきた」
【本来の意味】:議論や検討が十分に行われ、まもなく結論に達する段階を指します。「行き詰まる」とは別の意味です。
③「役不足」
(誤)「彼にその任務は役不足だ(=彼にとってその任務は重すぎる)」
(正)「彼にその任務は役不足だ(=彼にとってその任務は簡単すぎる)」
【本来の意味】:与えられた役割が、その人の能力に比べて軽すぎる場合に使います。力量が足りない場合は「力不足」「力が及ばない」が適切です。
④「気が置けない」
(誤)「あの人は気が置けないから、気を張ってしまう」
(正)「彼とは気が置けない関係なので、何でも話せる」
【本来の意味】:「気が置けない」の意味は、遠慮する必要がない、ごく親しい間柄であること。相手との間に、気を置かなくていいほど距離感が近いというニュアンスです。
おわりに
言葉は、単なる情報伝達の手段にとどまらず、相手に与える印象や信頼感、さらには人間関係の基盤を築く重要な役割を担っています。正しい日本語を使うことが大切であるのはもちろんですが、それ以上に「その場にふさわしい表現」を選ぶ力が求められます。いかに言葉づかいが正確であっても、状況にそぐわない表現や過度な敬語は、堅苦しさや違和感、場合によっては誤解や不快感を生む原因となることもあります。
言葉の選び方や表現の適切な使い分けは、学校教育だけではなかなか身につかない知識や感覚です。正確さだけでなく、「この場面ではどのような言い方が最も伝わるのだろうか」という柔軟な判断力を養うことも大切です。言葉への細やかな配慮や意識を持つ姿勢は、ビジネスの現場はもちろん、日常生活においても信頼や好感につながります。
この記事で紹介した注意点や具体的な表現の使い分けを、日々のメールや会話、書類作成などの場面で意識し、ぜひ実践してみてください。

![校正・校閲で役立つ辞書サイト[チェックしておきたいサイト一覧]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/04/Proofreading-and-Review-Sites.jpg)
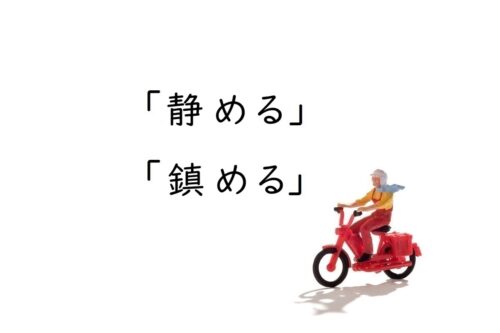






![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)
![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)
![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)
![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)
![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)
![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

